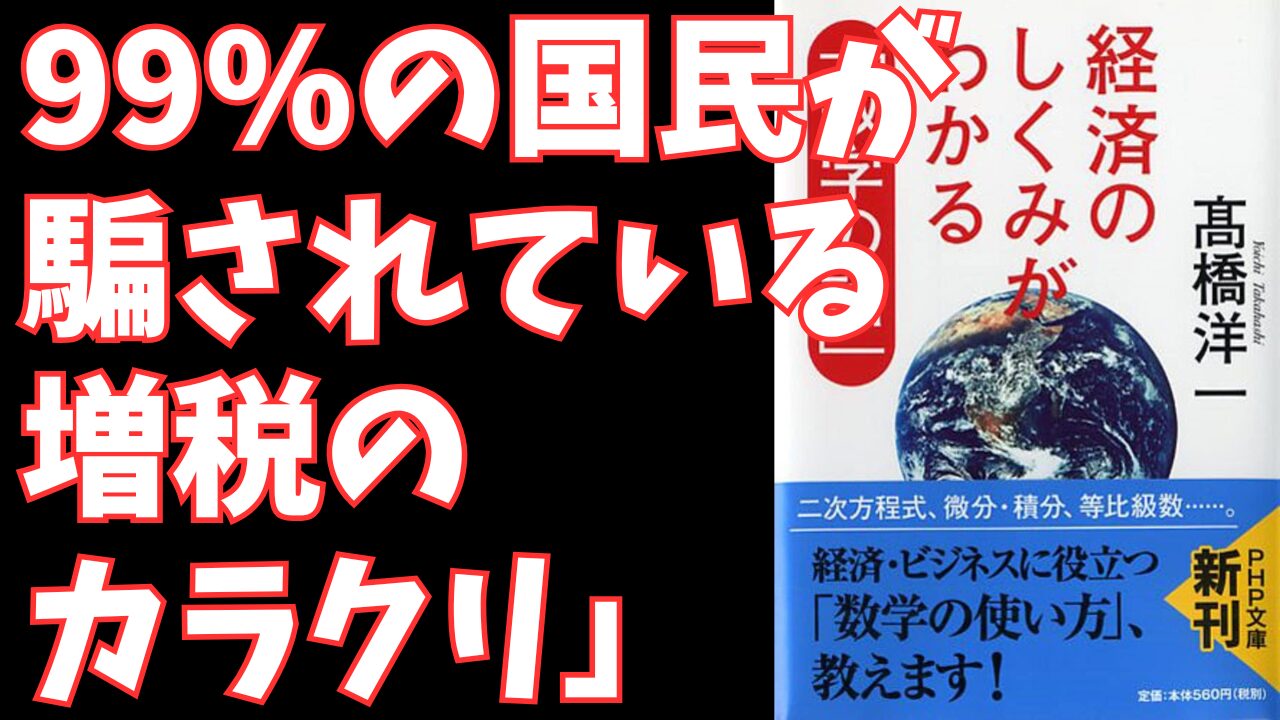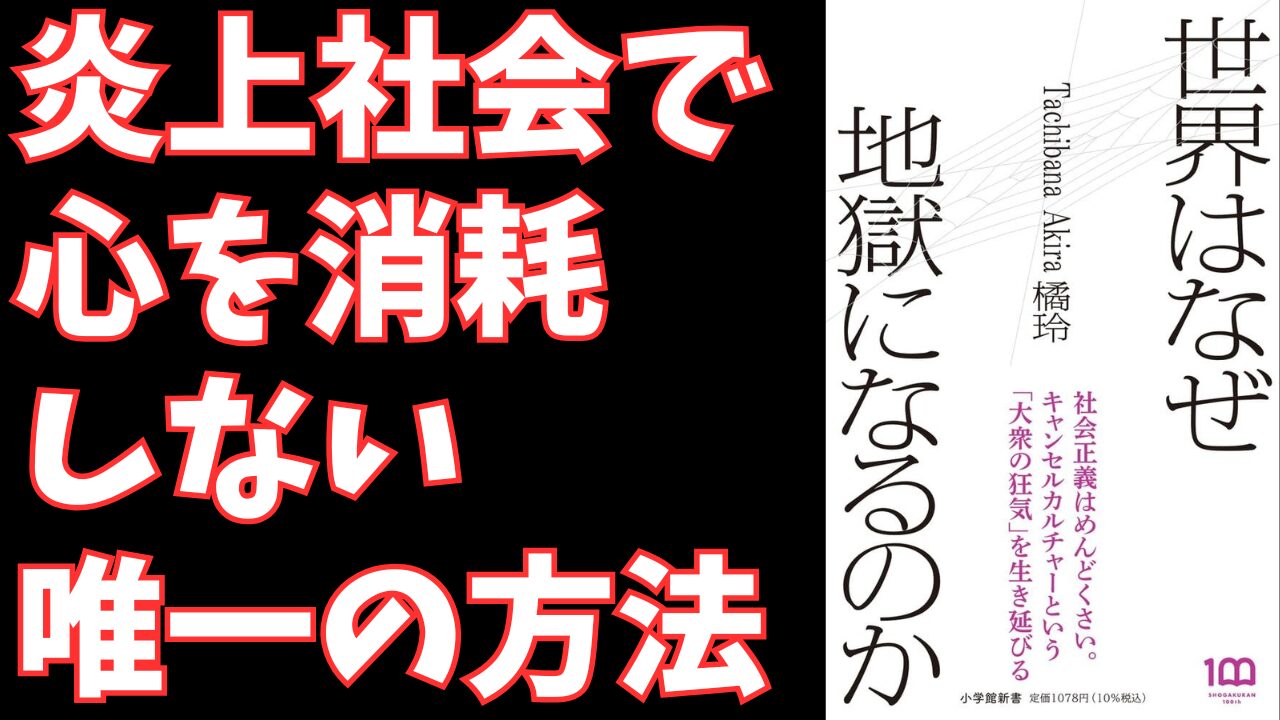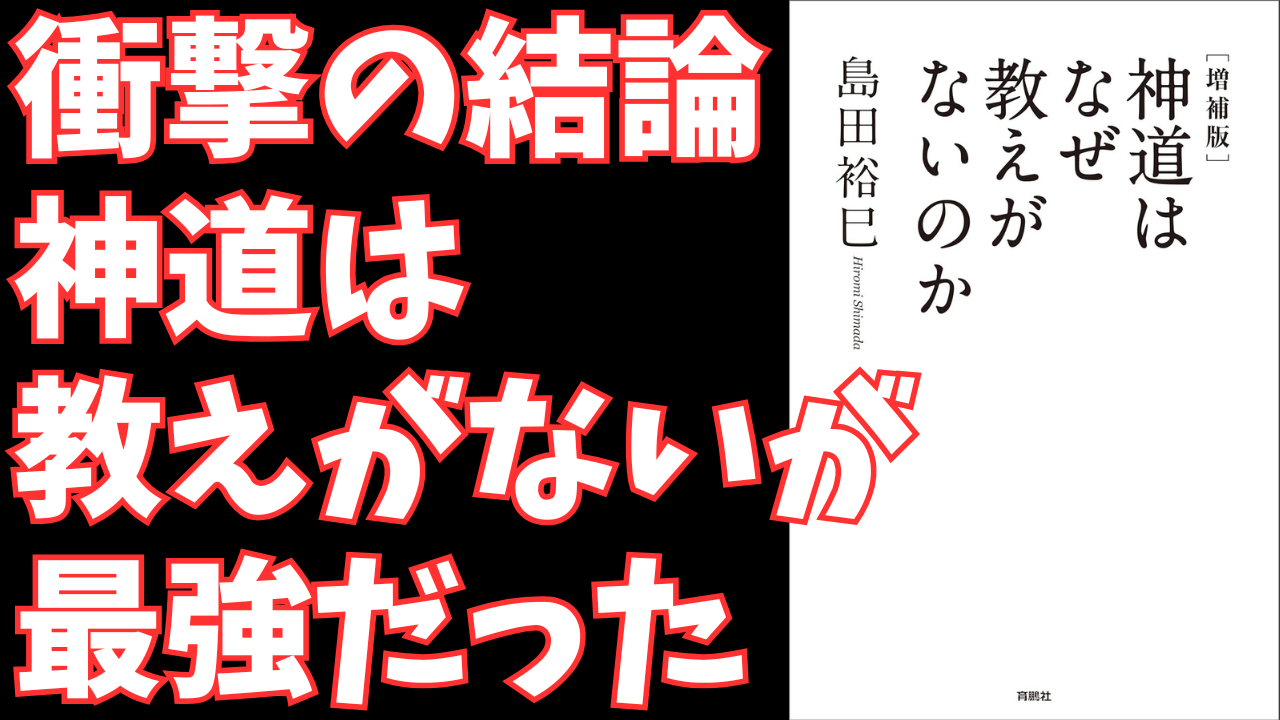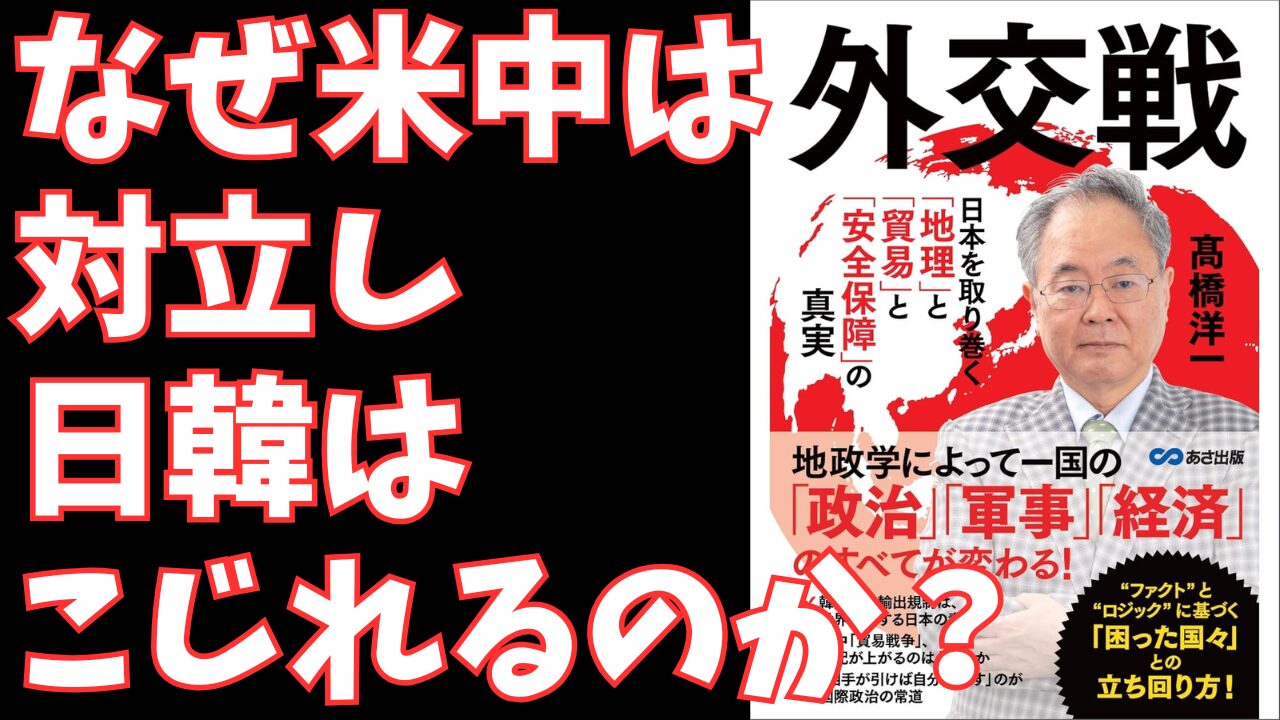『日本はどこに向かおうとしているのか』高橋洋一|国家予算とデータが暴く「失われた30年」の真実
本書『日本はどこに向かろうとしているのか 国家予算とデータから解き明かそう!』は、元財務官僚で数量政策学者の高橋洋一氏が、国家予算や客観的なデータに基づき、日本経済が抱える問題の本質を鋭くえぐり出す一冊です。
日経平均株価は最高値を更新する一方で、私たちの実質賃金は下がり続け、生活は楽になりません。多くの人が抱えるこの疑問に対し、著者は 「財務省やマスコミが流布する『財政危機』というプロパガンダが、緊縮財政を正当化し、日本を長期停滞に陥らせてきた」 と断言します。
本書を読めば、政府や日銀の政策決定の裏側、「国の借金」のカラクリ、円安の本当の意味、そして日本が再び成長するために本当に必要な政策が何なのか、ファクトに基づいた明確な視点を得ることができます。忙しいビジネスパーソンが、情報に惑わされず日本経済の未来を見通すための必読書と言えるでしょう。
本書の要点
- 日本の財政危機は嘘である。 政府と日銀を一体で捉える「統合政府」のバランスシートで見れば、日本の財政はG7で2番目に健全であり、財務省の言う「財政破綻」は起こり得ない。
- 円安は日本経済全体にはプラスである。 円安により政府が保有する外貨資産には数十兆円規模の含み益が出ており、これを減税などで国民に還元すれば、個人消費を活性化できる。
- 日銀の早すぎる金融引き締めはデフレへの逆戻りリスクを高める。 世界の中央銀行の鉄則である「ビハインド・ザ・カーブ」を無視した利上げは、景気の腰を折り、実質賃金をさらに悪化させる危険な政策である。
- 「失われた30年」の真犯人は緊縮財政である。 誤った財政観に基づき、公共投資や教育といった未来への投資を怠ってきたことが、日本の成長を阻害し、国際的な地位の低下を招いた。
- 専制国家に囲まれた日本は、タブーなき安全保障の議論が急務である。 米国の「グローバルパートナー」として、核共有の検討など、現実的な国防強化策を真剣に考えるべき時期に来ている。
なぜ、株価は好調なのに私たちの給料は上がらないのか?
2024年、日経平均株価はバブル期の最高値を更新し、経済ニュースは明るい見出しで溢れました。しかし、多くのビジネスパーソンにとって、その好景気を実感する機会は少なかったのではないでしょうか。むしろ、終わらない物価高と、 2年以上もマイナスが続く実質賃金 に、生活の苦しさを感じている方の方が多いかもしれません。
一方で、岸田政権は「異次元の少子化対策」や「新しい資本主義」を掲げながらも、その実態は「子育て支援金」という名の社会保険料上乗せや、効果の薄い政策ばかり。一体、この国はどこへ向かっているのか――。
そんな閉塞感を打ち破るのが、本書『日本はどこに向かおうとしているのか』です。著者の高橋洋一氏は、大蔵省(現・財務省)で日本の国家予算に深く関与し、小泉・安倍内閣ではブレーンとして活躍した経歴を持つ、まさに「霞が関の裏側」を知り尽くした人物。
本書では、高橋氏が一貫して主張してきた 「データに基づきファクトを直視すること」 の重要性が、日本経済のあらゆる局面を分析する上で貫かれています。なぜ、政府の減税は支持率向上に繋がらないのか? なぜ、実質賃金はいつまでも浮上しないのか? その答えは、政府・財務省・日銀が作り出す「デタラメな数字」と「プロパガンダ」にあると、本書は喝破します。
第1章:「国の借金1297兆円」は国民を騙すためのプロパガンダ
ニュースで「国の借金が過去最大を更新!」というフレーズを聞かない日はないでしょう。多くの国民がこれを鵜呑みにし、「日本の財政は破綻寸前だ。増税やむなし、緊縮財政も仕方ない」と思い込まされています。
しかし、高橋氏は 「この認識こそが、日本を30年もの長期停滞に陥れた最大の元凶だ」 と断言します。
バランスシートで見れば財政状況は一変する
なぜ「国の借金」という言葉がミスリードなのでしょうか。
本書が指摘する理由は明快です。それは、 政府の「負債」側だけを意図的に切り取り、「資産」を無視している からです。
例えば、民間企業であれば、負債(借入金)が多いだけで「倒産寸前だ」とは誰も言いません。必ず、資産と負債を両方記載したバランスシートを見て、純資産がどうなっているかで経営状態を判断します。
これは国家も同じです。財務省は「国債及び借入金」という負債だけを強調しますが、政府は年金積立金や外貨準備高など、莫大な金融資産を保有しています。
「統合政府」という考え方
さらに重要なのが、 政府と中央銀行(日銀)を一体とみなす「統合政府」 という視点です。
政府が発行する国債の多くは、日銀が買い入れています。これは、言わば「親会社(政府)の借金を、子会社(日銀)が肩代わりしている」ようなもの。連結決算で考えれば、親子間の貸し借りは相殺されるのが会計の常識です。
この「統合政府」のバランスシートで日本の財政状況を分析すると、驚くべき事実が浮かび上がります。国際通貨基金(IMF)のデータに基づけば、 日本の財政健全度はG7の中で、ドイツに次ぐ第2位 なのです。
(本書で示されるグラフをイメージしたものです)
「財政が厳しい」とされる日本が、なぜ健全なのでしょうか。その健全性を示す客観的なデータとして、本書は 国債の破綻確率を示す「CDSレート」 を挙げています。日本のCDSレートは世界で最も低い水準にあり、海外の投資家が「日本国債は極めて安全」と評価している証拠です。
財務省は、この不都合な真実を隠し、「国の借金」プロパガンダで国民の不安を煽り、増税と緊縮財政への流れを巧妙に作り出しているのです。
第2章:円安は悪ではない!日本経済復活への起爆剤
「円安で輸入品が高くなり、生活が苦しい」
これもまた、メディアが連日報道する「円安悪者論」です。確かに、個人の消費においてはマイナス面があることは事実です。
しかし、マクロ経済、つまり 日本という国全体で見れば、円安は大きなプラスの効果をもたらす と本書は解説します。
近隣窮乏化政策としての「自国通貨安」
経済学には「近隣窮乏化政策」という言葉があります。これは、自国の通貨を安くすることで輸出競争力を高め、他国の犠牲のもとに自国の経済を豊かにする政策を指します。トランプ前大統領が円安を「米国にとって大惨事だ」と批判したのは、まさにこの理論に基づいています。
実際に、経済協力開発機構(OECD)の経済モデルによれば、 10%の円安で日本のGDPは1~3年以内に0.4~1.2%増加する と試算されています。近年の日本企業の過去最高益も、この円安の恩恵が大きいのです。
政府が持つ「数十兆円の埋蔵金」を国民に還元せよ
そして、円安で最大の利益を得ているのは、実は日本政府です。
政府は「外国為替資金特別会計(外為特会)」で百数十兆円ものドル建て資産を保有しています。円安が進むことで、この資産の円換算額は膨れ上がり、 含み益は数十兆円規模 に達しています。
高橋氏は、この含み益、いわば「埋蔵金」を、 定額減税や給付金といった形で国民に還元すべき だと強く主張します。これを実行すれば、実質賃金のマイナスで冷え込んだ個人消費を一気に温め、経済の好循環を生み出すことができるのです。
第3章:なぜ日銀の「マイナス金利解除」は間違いだったのか
2024年3月、日銀はマイナス金利政策の解除を決定しました。メディアは「金利のある世界へ」「金融政策の正常化」と好意的に報じましたが、高橋氏はこれを 「完全にタイミングを間違えた」「デフレに逆戻りしかねない愚策」 だと厳しく批判します。
金融政策の鉄則「ビハインド・ザ・カーブ」
なぜ、利上げのタイミングが早すぎたのでしょうか。
それは、世界の中央銀行が守るべき鉄則である 「ビハインド・ザ・カーブ」 を無視したからです。
これは、物価が上昇し始めても、すぐには利上げせず、経済の動向を十分に見極めてから、意図的に「遅れて」金融引き締めを行うという原則です。なぜなら、性急な利上げは景気の芽を摘み、ようやく上向いてきた賃上げの勢いを止めてしまうリスクが非常に高いからです。
実際に、アメリカやヨーロッパの中央銀行は、インフレ率が目標の2%を大幅に超え、5%以上に達するまで利上げを見送りました。
一方、日本の日銀は、物価上昇の多くが輸入価格の高騰による「コストプッシュ型」であり、持続的な「ディマンドプル型」のインフレには至っていないにもかかわらず、わずかに目標を超えた段階で見切り発車してしまったのです。
雇用よりも金融機関を重視する日銀
では、なぜ日銀は利上げを急いだのでしょうか。
本書は、植田総裁の政策スタンスが 「国民の雇用や賃金」よりも「金融機関の経営」を重視している 点にあると指摘します。マイナス金利は、銀行の収益を圧迫するため、金融業界からは不評でした。今回の利上げは、デフレからの完全脱却という国民経済全体の利益よりも、金融機関への配慮が優先された結果だという見方です。
岸田政権が政治とカネの問題で機能不全に陥っている隙を突いて行われたこの政策転換は、日本のデフレ脱却を再び遅らせる大きなリスクをはらんでいます。
第4章:日本の未来を蝕む「間違った投資」
日本の「失われた30年」を生んだ根本原因は、財務省の緊縮財政にあると本書は繰り返し述べています。その悪影響が最も顕著に表れているのが、 未来への投資、すなわち「公共投資」と「教育投資」の欠如 です。
G7で唯一「公共投資」を減らし続けた日本
災害大国である日本にとって、インフラ整備は国民の安全・安心を守る上で不可欠です。しかし、驚くべきことに、 1995年以降、G7の中で公共投資を減らしているのは日本だけ です。他の国が2倍から4倍に増やしているのに対し、日本は約4割も減少させているのです。
この異常な事態を生んでいるのが、 「社会的割引率4%」 という、財務省が20年以上も見直していない不合理なルールです。これは、公共事業の費用対効果を計算する際の基準金利のようなもので、現在のゼロ金利に近い市場金利を考えれば、あまりに高すぎます。この高いハードルが、多くの有益な公共投資を阻んできたのです。
教育への投資を怠った国の末路
モノへの投資だけでなく、ヒトへの投資も日本は怠ってきました。国民生活の豊かさを示す国連の「人間開発指数(HDI)」で、日本の順位は1990年の6位から2022年には24位へと大きく後退しました。その最大の要因が、 教育水準の低下 です。
日本の公的教育費の対GDP比は、OECD加盟国の中で常に最下位レベル。財政緊縮派が教育予算を削り続けた結果が、国の競争力低下という形で表れているのです。
高橋氏は、少子化対策も「未来への人的投資」と捉え、現役世代の負担を増やす「子育て支援金」のような矛盾した政策ではなく、 財源を国債で賄う「教育国債」を発行すべき だと提言しています。
第5章:日本はどこへ向かうべきか? – 緊迫する国際情勢と安全保障
国内経済の問題に加え、本書は日本の外交・安全保障についても警鐘を鳴らします。ロシア、中国、北朝鮮という専制・独裁国家に囲まれた日本の地政学リスクは、かつてなく高まっています。
アメリカの「グローバルパートナー」としての覚悟
日米首脳会談で、日本はアメリカの「グローバルパートナー」と位置づけられました。これは、もはや日本の安全保障がアジア地域だけの問題ではなく、世界規模での貢献を求められていることを意味します。
ウクライナ支援や中東情勢への対応はもちろん、最も重要なのは中国との対峙です。 「台湾有事は日本有事である」 という認識のもと、日本は自らの防衛力を抜本的に強化する必要に迫られています。
タブーなき安全保障の議論を
高橋氏は、故・安倍晋三元首相が生前、議論の必要性を訴えていた 「核共有」 など、これまでタブーとされてきたテーマについても、現実的な選択肢として国民的な議論を始めるべきだと主張します。
また、中国恒大集団の破綻に象徴されるように、中国経済は長期停滞期に入ったと分析。日本は、経済的にも安全保障的にも、過度に中国に依存する関係を見直し、新たな国家戦略を構築しなければならないと結びます。
まとめ:データに基づき、自らの頭で考えるために
『日本はどこに向かおうとしているのか』は、単なる経済解説書ではありません。それは、政府やメディアが流す情報に踊らされることなく、私たち一人ひとりがデータという客観的な事実に基づいて日本の現状と未来を考えるための「思考の武器」を与えてくれる一冊です。
なぜ日本だけが30年も停滞しているのか。その答えは、 誤った経済認識に基づく、誤った政策の連続 にありました。
本書を羅針盤とすることで、私たちは財政、金融、外交、安全保障といった複雑な問題を貫く一本の筋を見出し、日本の進むべき正しい道筋を自ら見極めることができるようになるでしょう。情報過多の時代を生きる、すべてのビジネスパーソンにおすすめします。