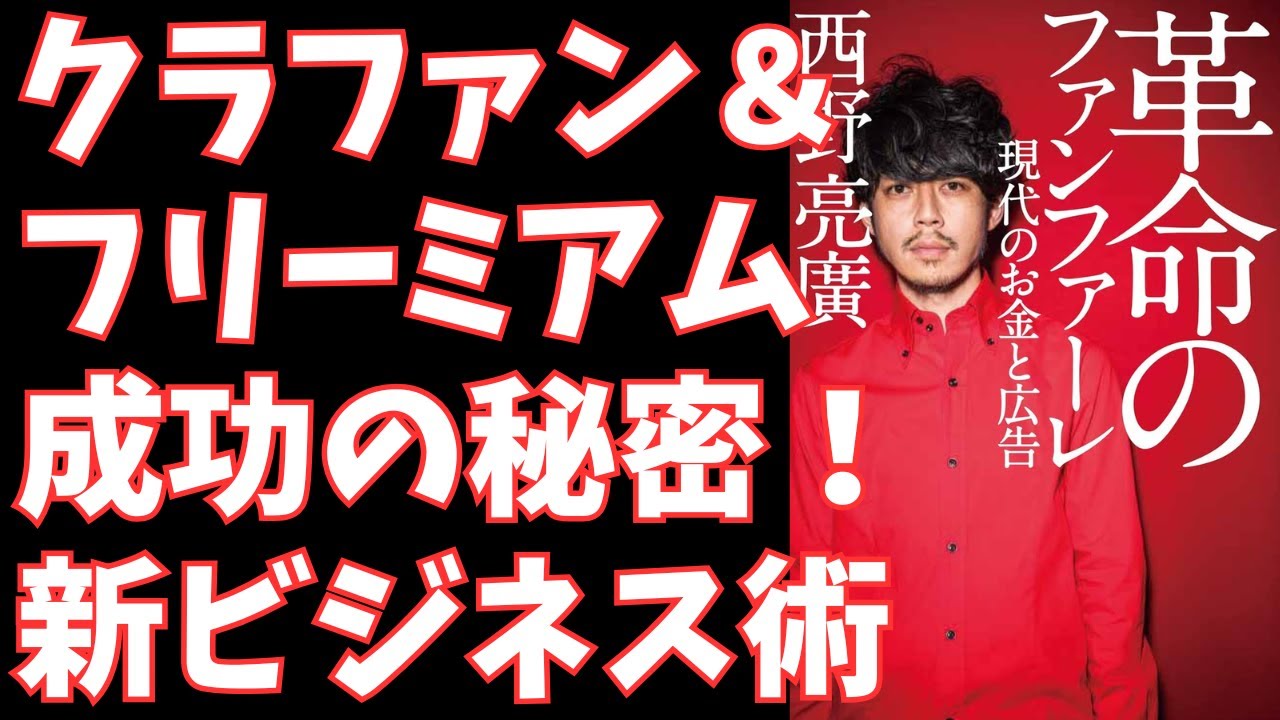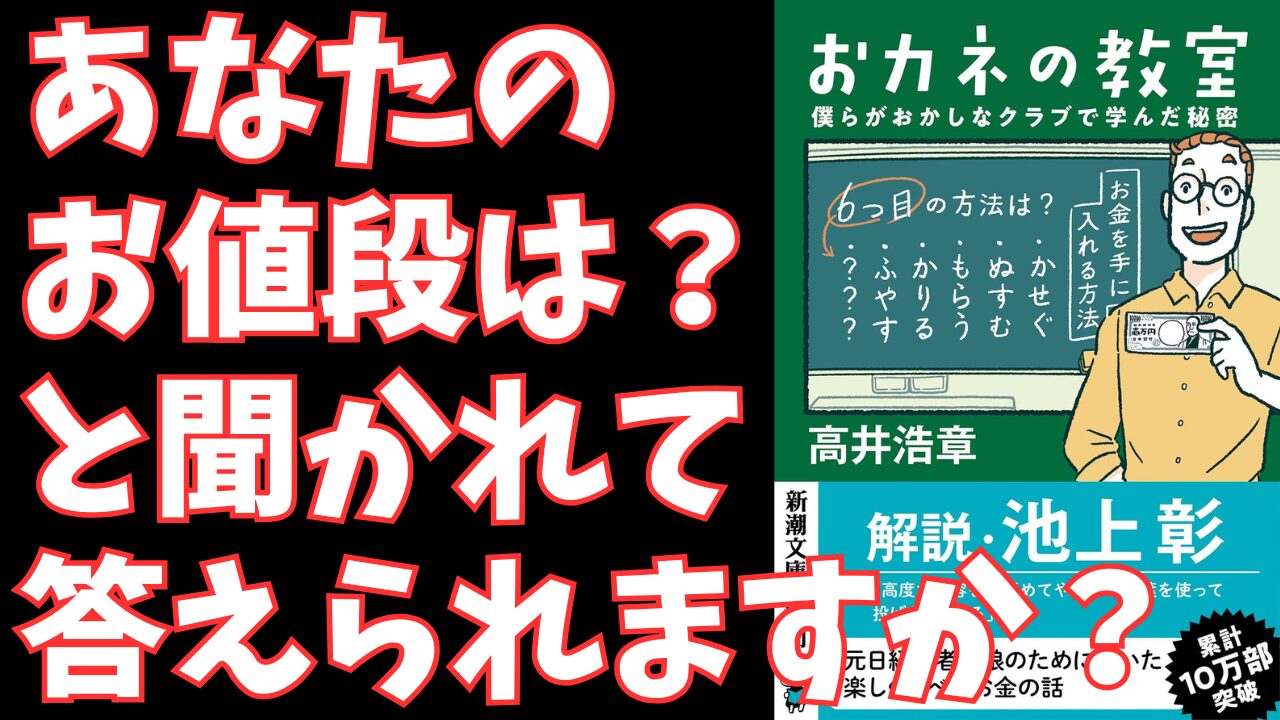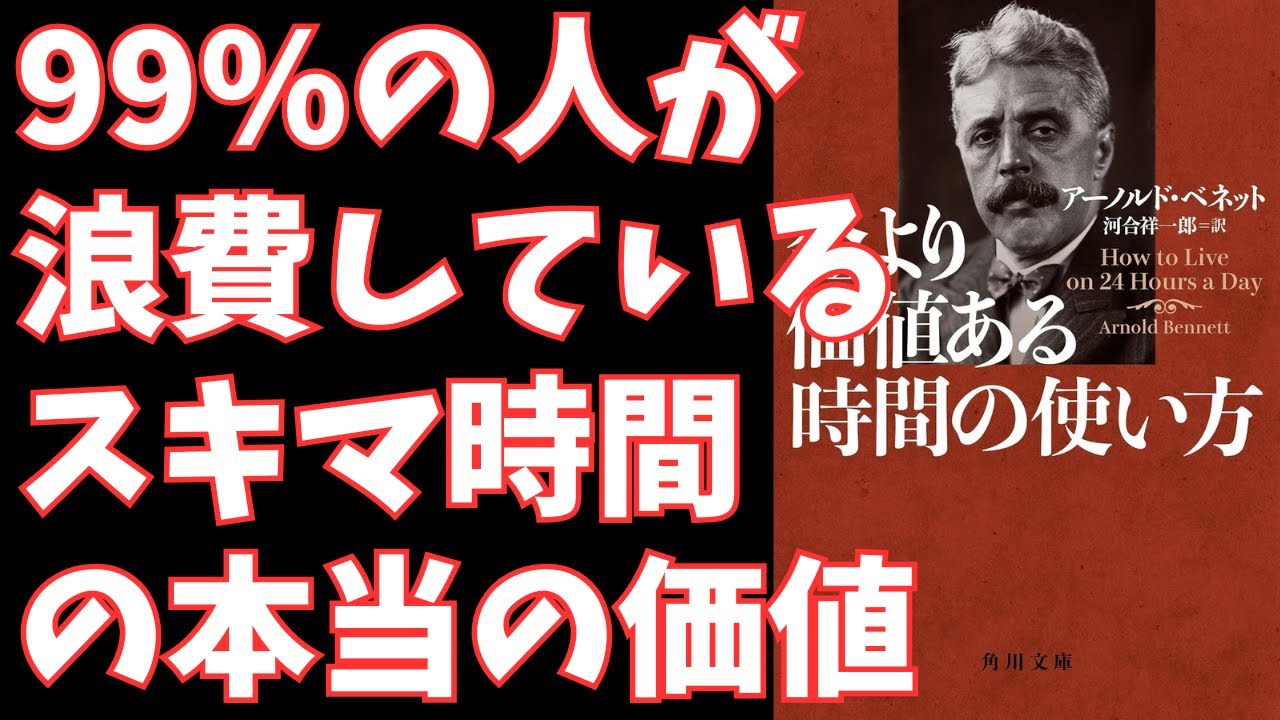『タピオカ屋はどこへいったのか?』に学ぶ、明日から使える儲かるビジネスの全技術
本書『タピオカ屋はどこへいったのか? 商売の始め方と儲け方がわかるビジネスのカラクリ』は、税理士である著者が、タピオカブームの終焉、立ち飲み屋の盛況、コンビニの商品戦略といった身近な現象を切り口に、商売で成功するための普遍的な原理原則を解き明かす一冊です。
なぜあるビジネスは流行り、廃れるのか。どうすれば顧客を集め、リピーターになってもらえるのか。利益を最大化する価格設定の秘訣とは何か。これらの問いに対し、社会の変化、消費者心理、コスト構造、立地戦略など、多角的な視点から具体的な事例を交えて解説しています。
この記事では、本書の中から特に忙しいビジネスパーソンに役立つエッセンスを厳選し、「社会変化とビジネスチャンス」「集客と消費者心理」「利益を生む値決めとコスト削減」という3つのテーマに再構成して、そのカラクリを詳しくお伝えします。明日からの仕事にすぐに活かせるヒントが、きっと見つかるはずです。
本書の要点
- 社会の変化や人々の「隙間」を捉えることが、新たなビジネスチャンスを生む。 流行やトレンド、働き方の変化といったマクロな視点が重要となる。
- 値決めの本質は「価値」の提供にある。 売り方や場所、見せ方を変えるだけで、同じ商品でも価格をコントロールし、利益を最大化できる。
- 集客の鍵は「消費者心理」の理解にある。 限定感や権威性、人との繋がりなどを巧みに活用することで、顧客を惹きつけ、熱心なファンを育てることができる。
- コスト構造を見直し、安定した収益モデルを築くことが持続的な経営に繋がる。 特に、フロー型からストック型のビジネスへ転換することは、現代のビジネスにおいて極めて重要である。
- 成功の秘訣は、自己流に固執せず成功事例から学び、挑戦し続ける姿勢にある。 天才的な発明ではなく、既存のビジネスの改良・改善にこそ多くのチャンスが眠っている。
はじめに:あなたの周りにも「ビジネスのヒント」は溢れている
「あれほど街に溢れていたタピオカ屋は、一体どこへ消えてしまったのだろう?」
「最近、立ち飲み屋で若い女性客をよく見かけるのはなぜだろう?」
「コンビニが日用品を当たり前のように売るようになったのはいつからだろう?」
私たちの日常には、こうした素朴な疑問が数多く存在します。本書『タピオカ屋はどこへいったのか?』は、まさにそうした身近な「なぜ?」こそが、ビジネスの本質を理解するための最高の入り口であると教えてくれます。
著者は、数多くの中小企業の財務をサポートしてきた税理士の菅原由一氏。彼の鋭い視点は、単なる流行り廃りの分析にとどまりません。社会の変化、消費者の心理、そして緻密なコスト計算といった「ビジネスのカラクリ」を、具体的な事例をもとに一つひとつ丁寧に解き明かしていきます。
この記事では、本書で紹介されている数々の事例の中から、特にビジネスパーソンが明日から自身の仕事に応用できる考え方やテクニックを厳選してご紹介します。読み終えるころには、あなたの見る世界が少し変わって見えるかもしれません。
第1章 社会変化を捉え、ビジネスチャンスに変える方法
成功するビジネスは、常に時代の風を読んでいます。社会がどのように変化し、人々のニーズがどこへ向かっているのかを敏感に察知することが、最初の重要なステップです。
なぜタピオカ屋は消え、立ち飲み屋が流行るのか?
2019年には「タピる」が流行語大賞トップ10入りするほどの社会現象となったタピオカブーム。 しかし、その多くはあっという間に姿を消しました。本書によれば、この背景にはプロダクトライフサイクルの視点が欠かせません。
直近のタピオカブームは、単なる「飲み物」としての価値だけではありませんでした。2017年に「インスタ映え」が流行語大賞に選ばれたように、SNSに投稿するための「撮影アイテム」としての価値、すなわち「コト消費」の側面が強かったのです。
ブームが去った後、生き残ったのは一部のチェーン店だけ。個人経営の多くは、唐揚げ店や焼き芋店など、次のブームへと乗り換えていきました。これができたのは、 少資金・省スペースで開業し、ブームが去る前に投資を回収するという「いつでも撤退できる」戦略 を取っていたからです。 一過性のブームに乗る際は、この「変わり身の早さ」が極めて重要なのです。
一方で、立ち飲み屋に若い女性客が増えている現象。これは「働き方改革」によって生まれた 「早く帰れるようになったが、まっすぐ帰りたくない」人たちの時間の隙間 を埋めたことが一因です。 さらに、「映画を倍速で見る」に代表される 「タイパ(タイムパフォーマンス)」を重視する若者の価値観 にもマッチしています。 短時間で気軽に飲める立ち飲み屋は、飲みニケーションを避けがちな若者でも「1時間だけなら」と誘いやすいのです。
また、コロナ禍を経て希薄になった「リアルな繋がり」を求める人々の受け皿にもなっています。立ち飲み屋は、社会の変化が生み出した複数の「隙間」を見事に埋めている好例と言えるでしょう。
コンビニが日用品を売る理由
今やコンビニでティッシュペーパーや洗剤を買うのは当たり前の光景です。これもまた、大きな社会変化を捉えた結果です。
その変化とは 「働く女性の増加」 です。1990年代に共働き世帯が専業主婦世帯を上回り、今やその差は2倍以上になっています。 日中に買い物をする時間がない働く女性にとって、夜遅くまで開いていて、職場や家の近くにあるコンビニは、スーパーの代わりとなり得る存在です。
セブン-イレブンのキャッチコピーが「開いててよかった」から「近くて便利」へと変わったように、コンビニが提供する価値も時代と共に変化しています。 スーパーで買えば安いとわかっていても、消費者はその 「便利さ」という価値に対して対価を払う のです。 これは、価格競争に陥りがちな商品を扱うすべてのビジネスにとって、大きなヒントとなるはずです。
第2章 顧客を掴んで離さない集客とブランド構築の心理学
どれだけ良い商品やサービスを持っていても、顧客に知ってもらい、選んでもらわなければ意味がありません。ここでは、顧客心理を巧みに利用した集客とブランディングの技術を見ていきましょう。
「限定」と「行列」が価値を生む
通販番組で「本日限定!」「限定100個!」といった言葉を耳にしない日はありません。これは、 「みんなと同じものは欲しくない」という心理(スノッブ効果) を刺激し、希少性を高めることで購買意欲を煽るテクニックです。 スープがなくなり次第終了するラーメン店や、入荷未定の人気商品に予約が殺到するアパレル店も同じ原理です。「手に入りにくい」という状況そのものが、価値となるのです。
また、インフルエンサーが紹介した商品が瞬く間に流行する現象は、 「流行に乗り遅れたくない」という心理(バンドワゴン効果) が働いています。 多くの人が支持しているものは、良いものに違いないと感じてしまうのです。
さらに、大手企業が莫大な費用をかけてテレビCMを打つのはなぜでしょうか。それは 「信用」を獲得するため です。CMでよく見かける企業、有名なタレントを起用している商品には、無意識のうちに安心感を抱きます。これは 「後光」を意味するハロー効果 と呼ばれる心理作用で、一つの特徴が全体の評価に影響を与える現象です。 この「信用」という無形資産が、優秀な人材や優良な取引先を引き寄せ、企業の成長を支える基盤となります。
なぜヤクルトレディは顧客との関係を維持できるのか?
AIや自動化が進む現代において、なぜヤクルトは訪問販売を続けるのでしょうか。その答えは 「ザイオンス効果」 にあります。これは、 繰り返し接することで、その対象への好感度や関心が高まる という心理効果です。
ヤクルトレディは、ただ商品を届けるだけではありません。顧客と世間話をしたり、健康に関する相談に乗ったりします。この 対話という人間的なコミュニケーションが、自動販売機にはない付加価値 を生み出しています。 特に、人との繋がりを求める高齢者などにとっては、このコミュニケーション自体が重要な価値となるのです。
これからの人手不足の時代において、 「人にしかできないこと」の価値はますます高まります。 効率化や自動化を進める一方で、どこに「人」の温かみを残すのか。その設計が、他社との決定的な差別化に繋がるのです。
第3章 利益を最大化する「値決め」と「コスト」のカラクリ
商売の生命線ともいえる「値決め」。そして、利益を直接左右する「コスト」。この2つを制する者がビジネスを制すると言っても過言ではありません。
1個2万円のメロンはなぜ売れるのか?
スーパーでは2,000円のメロンが、なぜ高級果物店「千疋屋」では2万円で売れるのでしょうか。その答えは、 千疋屋が売っているのは「メロン」ではなく「贈答品」だから です。
自分用に買うメロンと、大切な人への贈り物として買うメロンでは、消費者が求める価値が全く異なります。高級感のある箱やラッピング、そして「千疋屋」というブランド。それらすべてを含めての「贈答品」としての適正価格が2万円なのです。
この事例が示すのは、 「何を売るか」ではなく「誰に、どのような価値を売るか」で価格は決まる という事実です。自社の商品やサービスも、ターゲットや売り方を根本から見直すことで、全く新しい価格設定が可能になるかもしれません。
1000円カット店と無料スマホゲームの儲けの仕組み
低価格戦略で成功している例として、1000円カット店が挙げられます。彼らが利益を出せるのは、 徹底的な「引き算」の発想 にあります。
一般的な美容室が行うシャンプーやカラーリング、パーマといったサービスをすべてカットし、「髪を切る」という本質的なニーズに特化。これにより、水回り設備などの初期投資を抑え、一人当たりの施術時間を大幅に短縮し、圧倒的な回転率を実現しているのです。 多機能・高サービス化とは真逆の、「シンプルさ」を追求したことが成功要因です。
一方で、「無料」という最強の価格設定で市場を席巻しているのがスマホゲームです。これは 「フリーミアムモデル」 と呼ばれる戦略です。 まずは無料で多くのユーザーを獲得し、その中のごく一部(一般的に5%程度と言われる)のユーザーがアイテム課金などを行うことで、全体の収益を支える構造です。 最初に無料で使ってもらい、その価値を実感した上で課金してもらう。このモデルは、あらゆるデジタルコンテンツに応用可能な強力な手法です。
安定経営の鍵は「ストック型ビジネス」にある
GAFAのような巨大IT企業がなぜサブスクリプションサービスを重視するのか。それは、 ビジネスモデルを「フロー型」から「ストック型」へと転換するため です。
タピオカ屋のように、一回ごとの販売で収益を上げるのがフロー型。収益が不安定で、ブームが去ると一気に経営が傾きます。 対して、サブスクのように月額課金などで継続的に収益を得るのがストック型。大きな収益の波はありませんが、 収益が安定し、将来の予測が立てやすくなる という絶大なメリットがあります。
収益が安定すれば、新たなサービス開発への投資もしやすくなり、金融機関からの信用も高まります。 著者は「どんな商品もサブスク化できる」と断言します。自社のビジネスをいかにしてストック型に近づけられるか。この問いを持つことが、サステナブルな経営への第一歩となります。
まとめ:成功する経営者に共通する、たった2つのこと
本書は、数多くのビジネスのカラクリを解き明かしてきましたが、著者は最後に、自身が支援してきた「儲かっている経営者」に共通する、2つの重要な姿勢を挙げています。
一つ目は、自己流にこだわらないこと。
多くの人は、スティーブ・ジョブズのようなゼロからイチを生み出す天才的な発明を目指しがちです。しかし、ビジネスチャンスの多くは、 既存のサービスや商品を観察し、「もっとこうすれば便利になるのに」という不満や不便を解消する ところに眠っています。成功事例を徹底的に分析し、良い部分を自社に取り入れる素直さが重要です。
二つ目は、挑戦をあきらめないこと。
事業づくりは簡単ではありません。一度の挑戦で成功するケースは稀です。しかし、成功する経営者は、目標達成への強い欲求を持ち、失敗を恐れずに行動し続けます。人気マンガのセリフにもあるように、「あきらめたらそこで試合終了」なのです。
私たちの周りには、ビジネスのヒントが無限に転がっています。本書を片手に街を歩けば、昨日までとは違う景色が見えてくるはずです。日常に潜む「なぜ?」を深く掘り下げ、自分なりの答えを探す。その探求心こそが、あなたのビジネスを次のステージへと導く原動力となるでしょう。