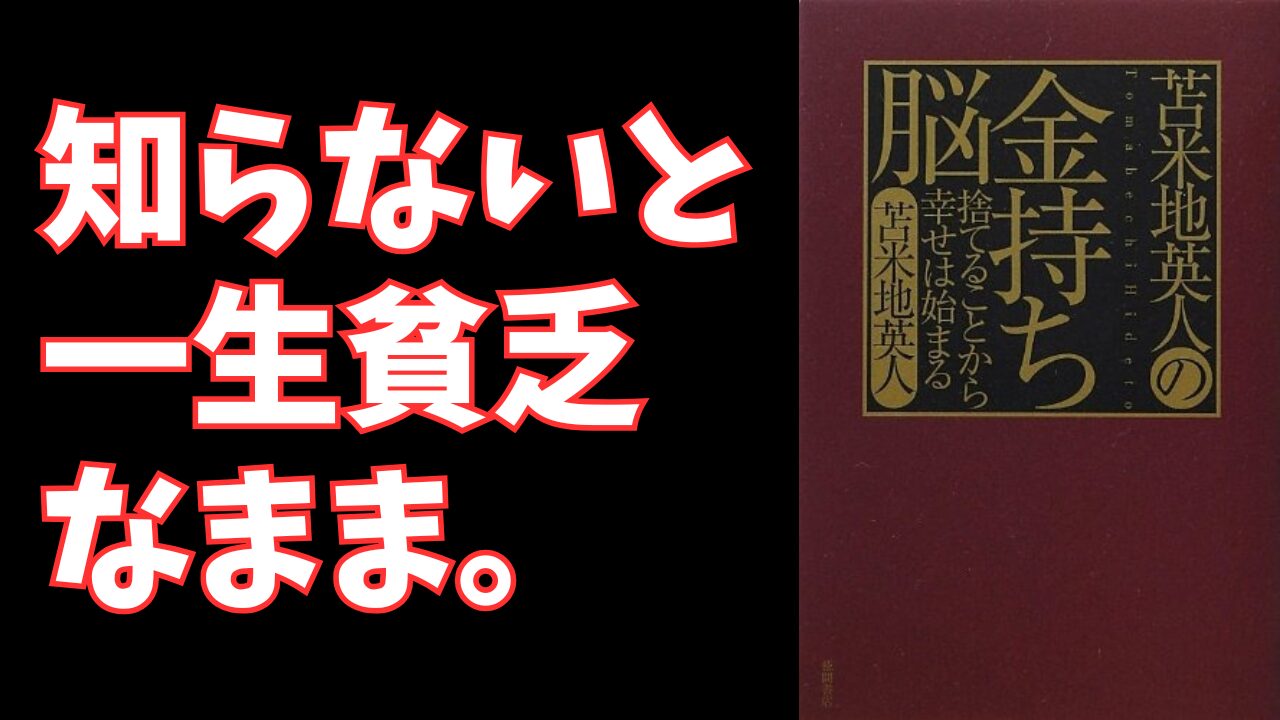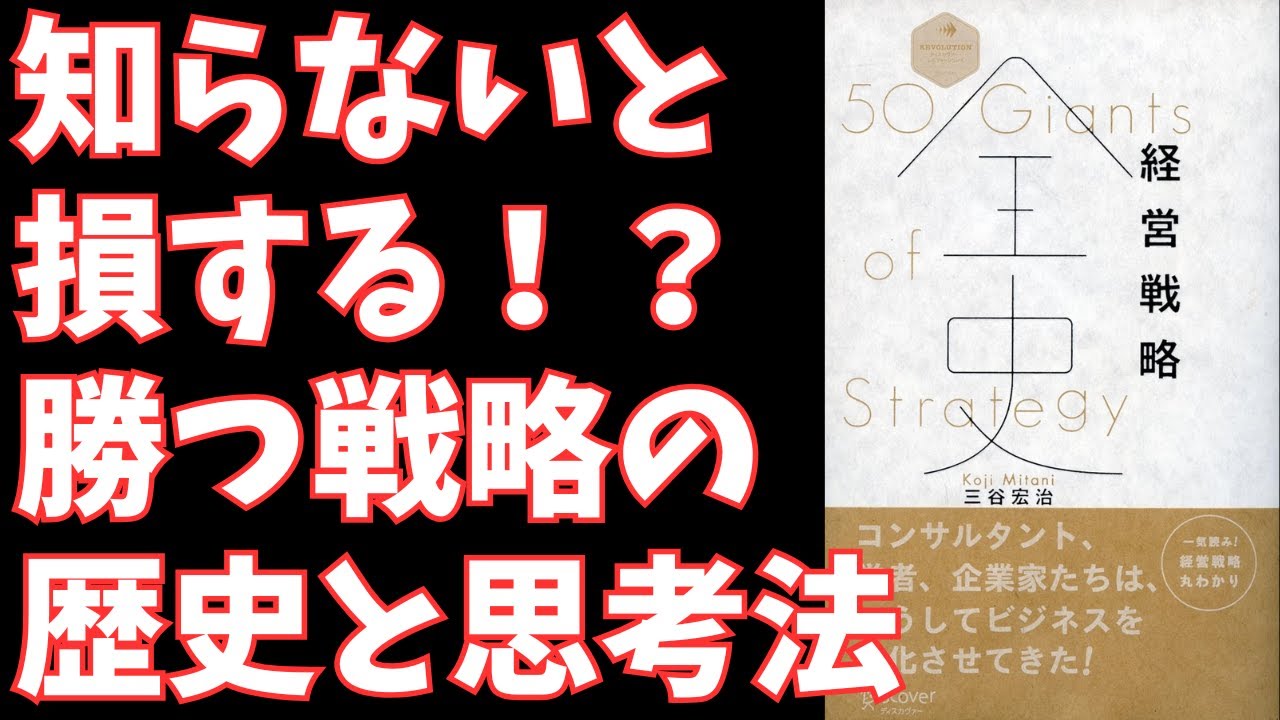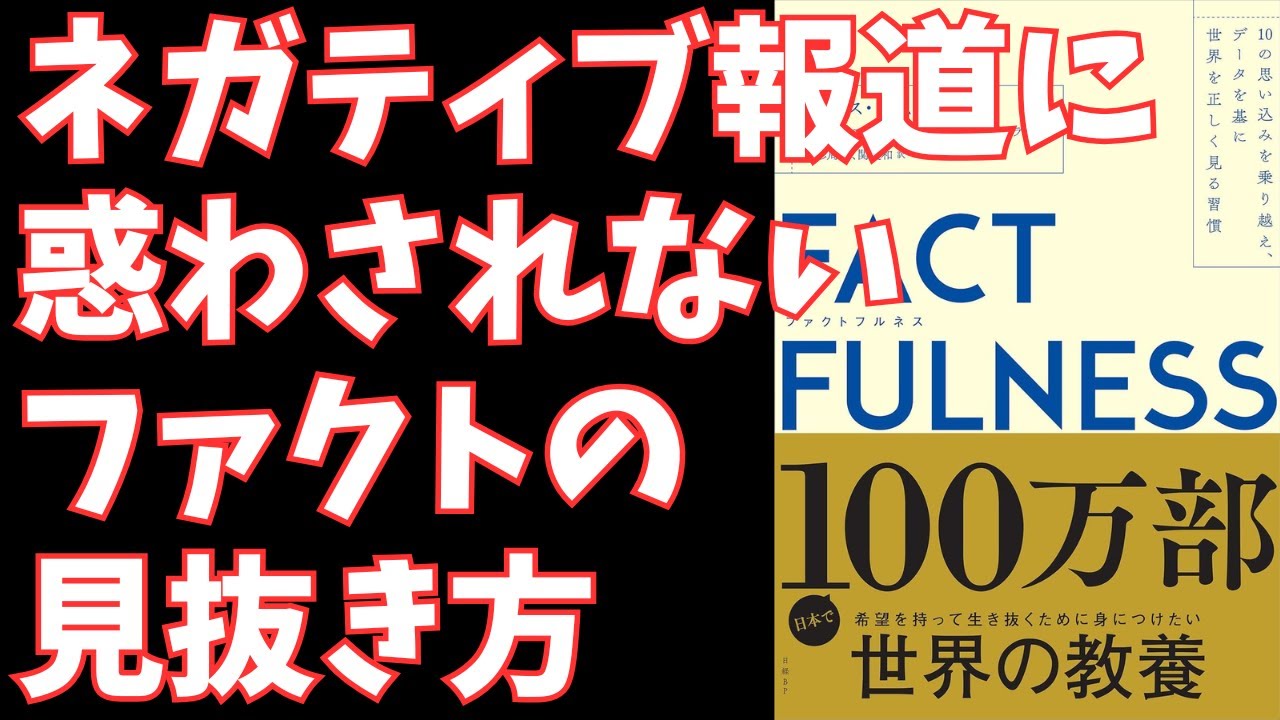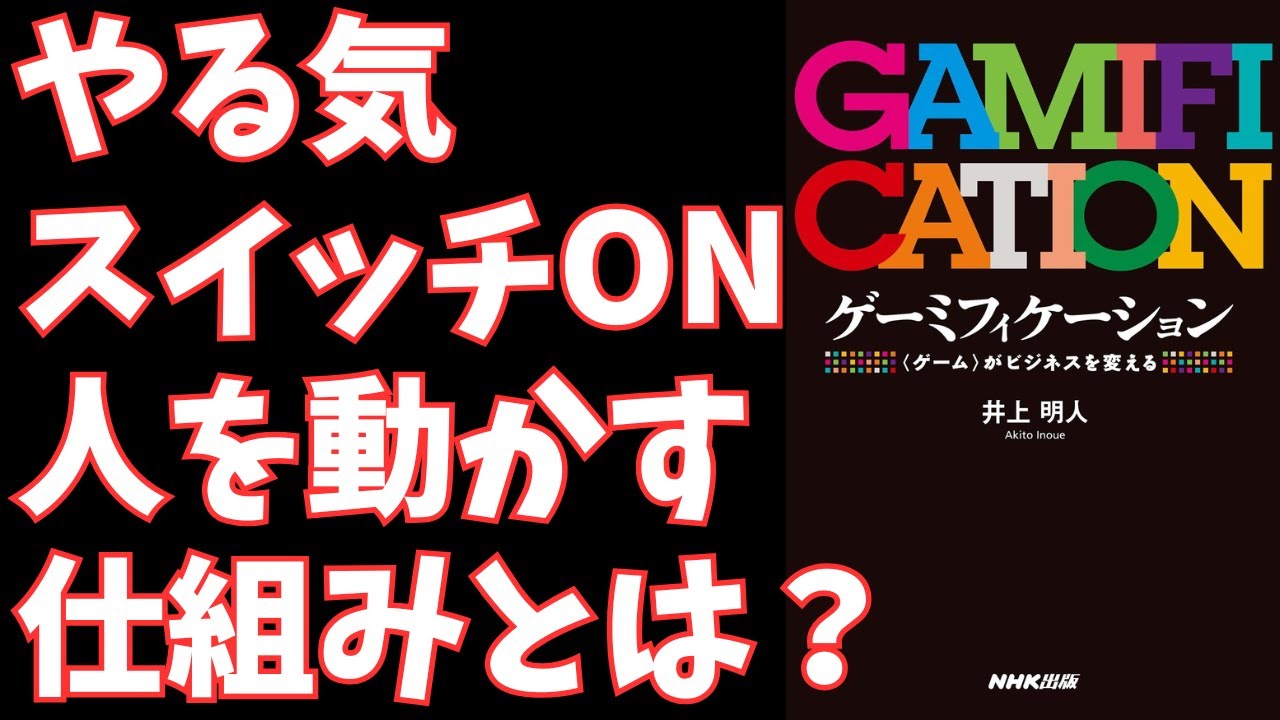グローバル時代における働き方2.0と4.0:不条理な会社人生から自由になるヒント
本記事では、急速なテクノロジーの進歩とグローバル化の時代において、これまで日本が当たり前と信じてきた雇用慣行や働き方がなぜ限界に達しつつあるのか、その実態を具体的なデータや事例から探ります。そして、いま世界の先端で広がっている「働き方2.0」「働き方4.0」がいかなる特徴を持ち、日本の前近代的ともいえる雇用制度を抜け出すうえでどのようなヒントを与えてくれるのかを解説します。企業文化やマネジメント、エンゲージメントの視点から生まれる不条理への対策を示し、個人がこれからの社会をどう生き延びるか、自由にキャリアを築くにはどうしたらよいかを論じます。
働き方2.0と4.0が示す未来とは
日本の雇用慣行は、戦後から高度経済成長期にかけて「年功序列・終身雇用」という形で確立されました。企業と社員が一体化したような「家族主義」が機能した背景には、経済が右肩上がりに拡大し、人手不足に対処するために定年まで安定を保証する“日本型雇用”が求められた、という時代的事情があります。
しかし、そのモデルは「働き方1.0」として大きな機能不全をきたし、近年では「働き方2.0」の到来が叫ばれてきました。これは、成果主義をベースとしたよりグローバルスタンダードに近い働き方を指します。ところが世界を見渡すと、すでに2.0で止まらず、フリーエージェント(ギグエコノミー)へ移行する働き方4.0の潮流がより大きなうねりとして到来しつつあるのです。
- 働き方1.0:年功序列と終身雇用に支えられた昭和的スタイル
- 働き方2.0:成果主義に基づくグローバル標準(しかし時代的にはやや古い)
- 働き方3.0:プロジェクト単位で専門家が離合集散するシリコンバレー型
- 働き方4.0:組織を持たず、個人が自由な契約を結ぶフリーエージェント型
- 働き方5.0:AIやロボットが仕事をほとんど担う近未来的ユートピア/ディストピア
このなかで日本の改革は1.0から2.0への過渡期にとどまり、さらに先を行く3.0や4.0には追いついていない状態です。フリーランスやギグワーカーの増加、AIの台頭による働き方やビジネスモデルの変革が起こるなか、いまだに「解雇が困難」「年功序列が実質的に残る」「女性が昇進しづらい」といった不合理が日本社会を縛り続けています。
日本人が仕事を嫌いになる理由
さまざまな調査で、日本人のエンゲージメント(仕事や会社に対する愛着心)が世界的に見ても極端に低いことが示されています。例えばギャラップ調査では、日本人で「仕事に熱意を持っている」労働者の割合はごくわずかだと報告され、世界最低水準を記録してきました。欧米と比べて給与水準が低いわけでもないし、一定の福利厚生や雇用保障があるにもかかわらず、社員がまるで会社に感謝していないかのように見えるのはなぜなのでしょうか。
大きな理由として、
- 雇用の強制力が強く、個人の自主性が尊重されにくい
- 年功序列で努力よりも年齢や勤務年数を重視してきた
- 転勤、異動、出向などがしばしば“命令”として行われる
といった構造があります。おまけに正社員と非正規の格差が激しく、非正規の労働条件の悪さや「身分差別」が遠因となっているケースも多いのです。
さらに、長時間労働の割に生産性が低いと指摘される日本は、会社を憎んでいる社員が多いわりに、過労死するほど働いても利益に結びつかないという奇妙な状態に陥っています。
グローバル企業で見る「働きやすさ」の正体
一方、検索やSNS、電子商取引などを担うプラットフォーマー企業(いわゆるGAFA)に代表されるグローバル企業は、以下のような方針を打ち立てています。
- 最高の人材だけを集め、突出した報酬を与える
- 解雇も含めてルールを明文化し、合理的に対処する
- 能力が発揮できない社員には、早めに「別の道」を提示する
有名な映像配信会社が公開した「カルチャーデック」でも、成果を追求し続けるプロスポーツチームさながらの組織づくりを目指す様子が明記されています。彼らは「社員をファミリーとして養う」のではなく、「最高の人材同士が切磋琢磨する環境」を最重視しているのです。結果的に年俸数千万〜億単位も珍しくなく、実力を十分に発揮できなければ早期退職勧奨(または解雇)を受ける代わりに、辞めても経歴や評判を武器にすぐ別の新天地へ行ける、という極めてフラットな流動性が保たれています。
こうした「プロスポーツ型」の組織では、成果が見えやすいエンジニアリングや研究開発などが報酬の高い専門職として尊重される一方、硬直化した人事制度で評価軸が曖昧な組織は国際競争で苦戦を強いられやすいといえるでしょう。
ギグエコノミーはフリーエージェントの時代へ
働き方4.0の本質は、個人で仕事を受注するギグエコノミーにあります。たとえばライドシェアや民泊などを手掛けるシェアリングサービス企業がプラットフォームを用意すると、ドライバーやホストは企業に所属せずとも仕事を得られます。
また、専門的スキルを持つフリーランスも、複数の人材プラットフォームに登録すれば世界中からの案件にアクセス可能です。こうした動きに「自由度」や「ワークライフバランスの取りやすさ」を見出す人は増えています。調査でも、インディペンデントワーカーの多くが「会社員時代より幸福感が高まった」と答えているのです。
ただし、ギグエコノミーには以下のようなリスクも指摘されています。
- 報酬の不払い問題(フリーランスへの支払いが一方的に拒否されるなど)
- 保険・年金などの福利厚生が無いために老後不安が大きい
- 常に評判と評価が公開され、自己管理が必須
このように光と影の両面があるものの、企業も人材も「必要なとき、必要な契約だけを結ぶ」メリットを実感しており、既存の正社員システムより柔軟性に優れる形態として注目されています。
日本型雇用はなぜ不条理なのか
日本の「雇用1.0」的慣行が深く根を張っている背景には、戸籍制度がイエ単位で続き、家族観や会社観もイエに基づいてきたという歴史があります。定年制や年功序列、企業内の管理職構造も「男性正社員が家庭を守り、企業はその男たちを雇用で守る」という仕組みに由来し、女性や非正規には不利な面が残っています。
さらに、
- 転勤・異動が一方的に行われる
- 外国人労働者への「身分」格差(現地採用と本社採用の違いなど)
- 「不合理な格差禁止」や「同一労働同一賃金」が徹底されにくい
といった問題も、すべては「会社を正社員の共同体」として擁護し続ける時代遅れの名残です。実際、定年制を年齢差別だとする考え方は国際的には当たり前で、欧米には定年そのものが法律で禁止されている国もあるのです。
しかし日本は定年を一種の強制解雇として、再雇用の名目で給与を下げたり、まったく別の業務につけるやり方を続けています。それでも長年の習慣として大多数が問題視してこなかったのは、「日本型雇用が日本を幸福にしてきた」という幻想や刷り込みが根強いためでしょう。
会社や管理職はこれからなくなるのか
急激なテクノロジー進化やギグエコノミーの拡大を見れば、「組織に所属するよりフリーで働くほうが自然だ」という見方もあります。実際、今後AIが多くの業務を自動化し、プロジェクト単位で人員を集めればよいという形になるなら、企業という大きな器を保有する必然性は薄れるかもしれません。
一方で、組織があるからこそできる仕事やプロジェクトも存在します。「開発費用を莫大に投じる大型投資」や「社会的インフラの整備」などは大規模な会社・組織体なしには動かしにくいのも事実です。
したがって「会社」自体が完全になくなる可能性は低いにせよ、働き方の多様化は確実に進みます。専門領域ごとに個人が自分の評判とスキルを生かして複数のチームを渡り歩くスタイルが増え、「管理職」に当たる立場はそこまで多くは必要ない、という方向には向かうでしょう。
これからの生き延び方:自分の看板を育てる
世界が本格的に2.0や4.0へ移っていく潮流の中で、日本企業の不合理を嘆き続けても解決にはなりません。むしろ一人ひとりが、自分の手でキャリアや未来を切り拓く「自己責任のリベラルな時代」に突入しているのです。
ここで重要なのは、以下のステップを意識することです。
- 専門スキルや実績を可視化し、市場価値を高める
- 国内外問わず、スペシャリストとして認められる強みを育てる
- オープンなSNSなどで実績や成果を積極的に発信する
- 外部ネットワークやコミュニティに積極参加する
- 会社の看板がなくとも動けるつながりを持つ
- 同業他社との情報交換や勉強会で視野を広げる
- 「好きなことで生きていく」だけではなく「食べていく」仕組みを作る
- 趣味や情熱を仕事化するなら、収入化のルートとファン(顧客)育成が欠かせない
- ギグワークなら複数のプラットフォームを活用し、リスクを分散する
- 日本型雇用や正社員へのこだわりを捨てる
- 退職金などの長期的報酬や「名刺の力」から離れたとき、どれだけ自分が強くいられるか
- 転職や副業・起業も視野に入れ、「不条理なルール」にずっと縛られない道を探す
- いつからでも、どこからでも学び直せると知る
- 新しい技術や資格取得のためのオンライン学習環境は格段に充実
- 年齢にとらわれず、好奇心を維持しながら専門性をアップデートし続ける
こうした方向性を目指すことで、個人がより自由に働く道が開けます。また、会社自体も「新卒採用と長期雇用」の硬直したルートを見直し、流動性を上げなければ優秀な人材を確保できない時代に入っています。企業も個人も、短期的には痛みがあっても新しいシステムを模索しなければ、海外の競合企業や新規参入プレーヤーにどんどん置いていかれるでしょう。
不条理から自由になるために
本書(元となった資料)で強調されているのは、テクノロジーの急激な進展が雇用の未来を変える中心的要因であることです。リモートワークやAIの活用が進めば、企業の中にいながらすべてを抱え込む必要はなく、外部と協業しながら柔軟に働く手法が最適解になるケースが増えます。
同時に、「日本人の大多数が会社を憎んでいる」ほどにエンゲージメントが低い現場をこのままにしておくと、イノベーションが生まれる余地も失われていくでしょう。
「結局は個人次第」という冷酷な現実がある一方で、自由に動き回れる人材は自分の力を最も発揮できる場を求めて世界を巡ることができます。高い専門性を持つエンジニアが世界の超大手IT企業に流れていく構図はNTTや大手電機メーカーなどで既に起こっています。
日本企業も「社員をファミリーとして養う」「メンバーシップを重んじて定年まで雇用を守る」という古い価値観だけでは、優秀な人材の離脱を止められないのです。
不条理を超える術は、組織の破壊や極端な個人主義ではなく、仕事にリアルタイムで価値を見いだせる環境整備だといえます。配置転換や異動命令を盾にするのでなく、社員一人ひとりの意欲やスキルに合った活躍の場を用意し、業績が伴わない部署やプロジェクトは速やかに断念して別の道を示す。そんな透明性と大胆な割り切りが、海外の先端企業の事例から見ても求められているのです。
まとめ
- 日本の働き方1.0は年功序列と終身雇用に支えられた高度成長期の遺物
- しかし、世界では既に2.0(成果主義)から3.0、そして4.0(フリーエージェント)へと変化
- テクノロジーとグローバル化が雇用慣行を根底から揺るがし、イエ単位の身分制度は限界
- 同時にギグエコノミーもリスクはあるが大きな可能性を秘め、個人の自由度を高める流れが加速
- 企業も個人も、世界標準のリベラルなルールを受け入れ、人材が移動しやすい環境を整える必要がある
- 不条理な会社人生から解放されるには、自己の専門性と評判資本を磨き、自らの看板を築くことが不可欠
やみくもに「日本型雇用を守れ」と叫んでも、いずれテクノロジーの進展やグローバル競争に飲み込まれてしまいます。自分自身の価値を高め、自分に合った働き方を柔軟に実践していく――それこそが次の時代を生き抜くための最善策であり、誰もが不条理から自由になるための第一歩なのです。