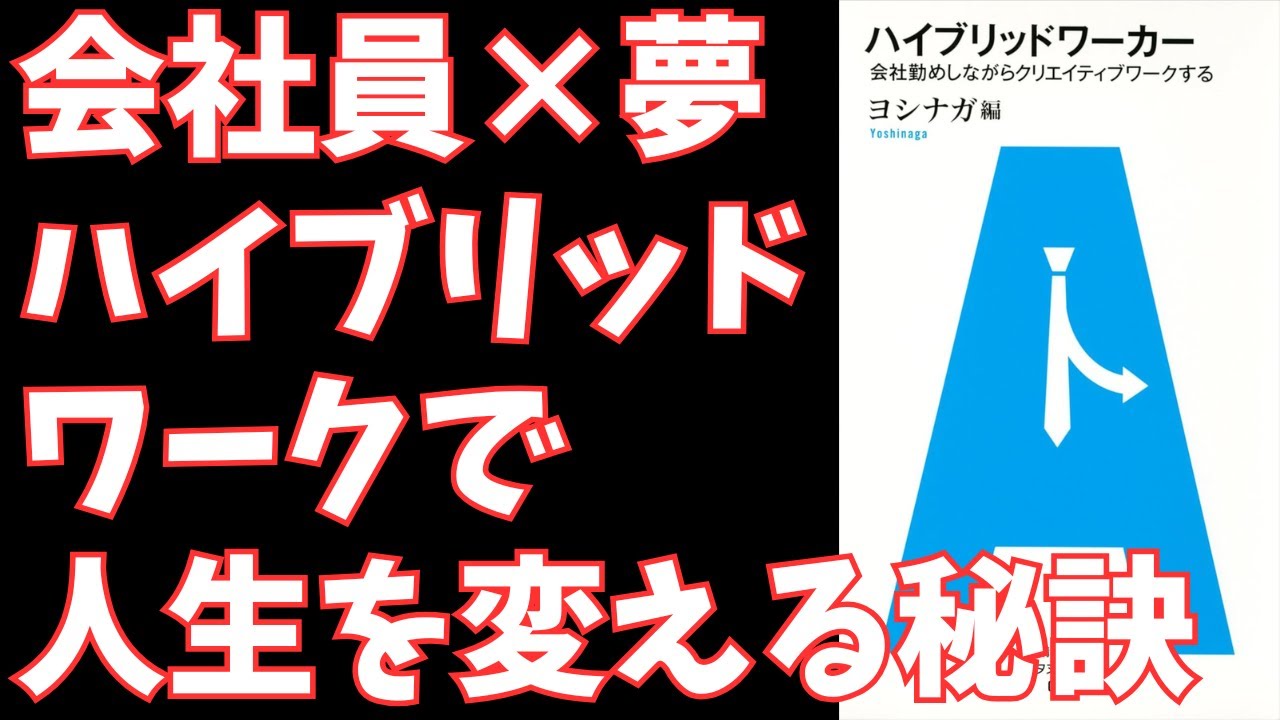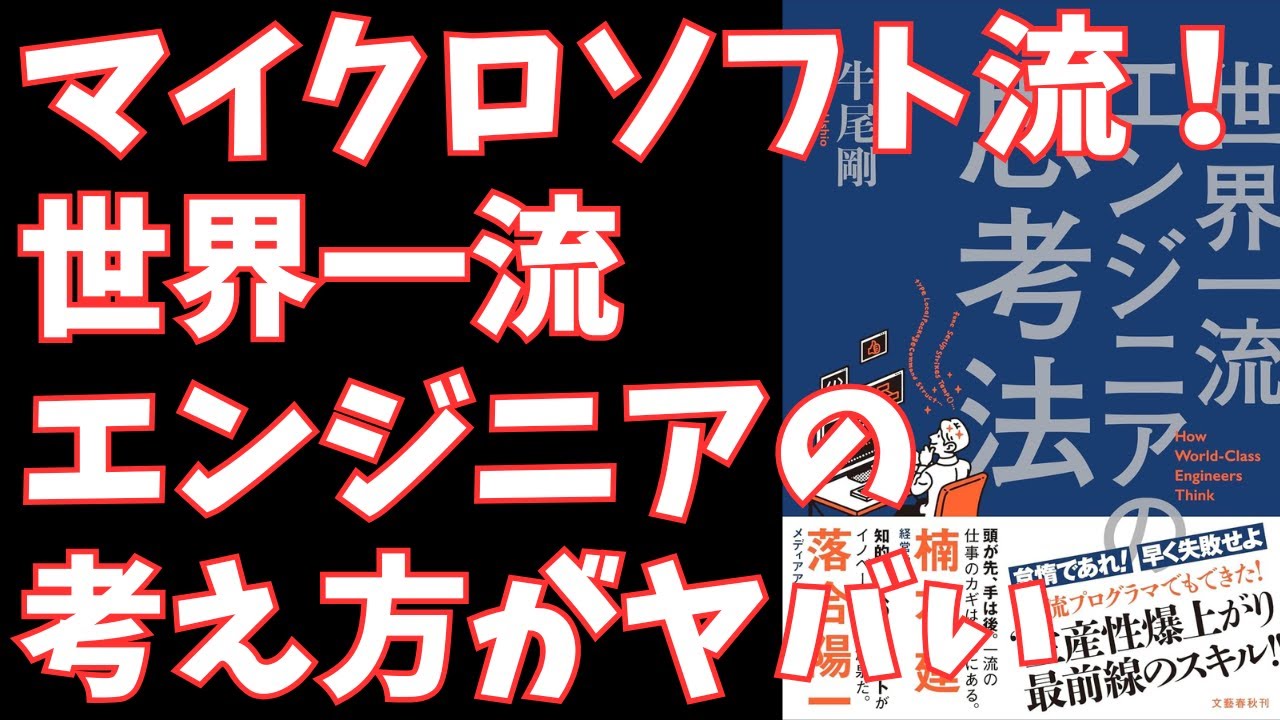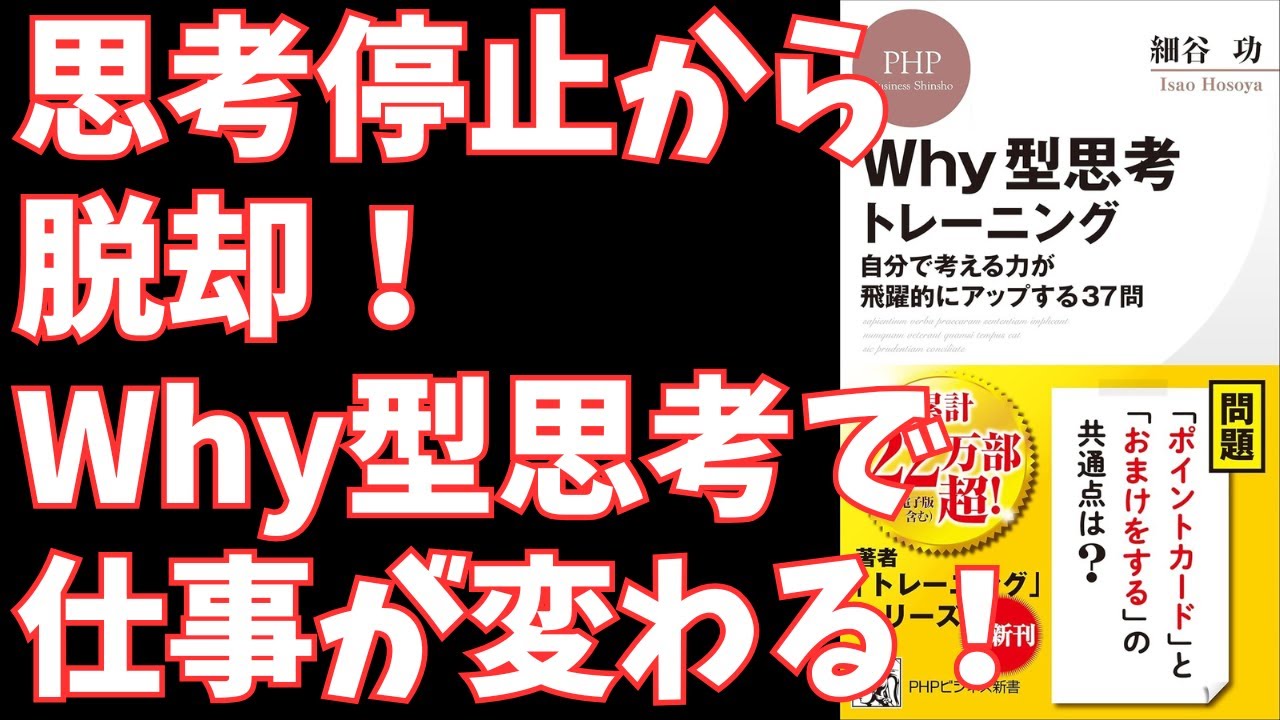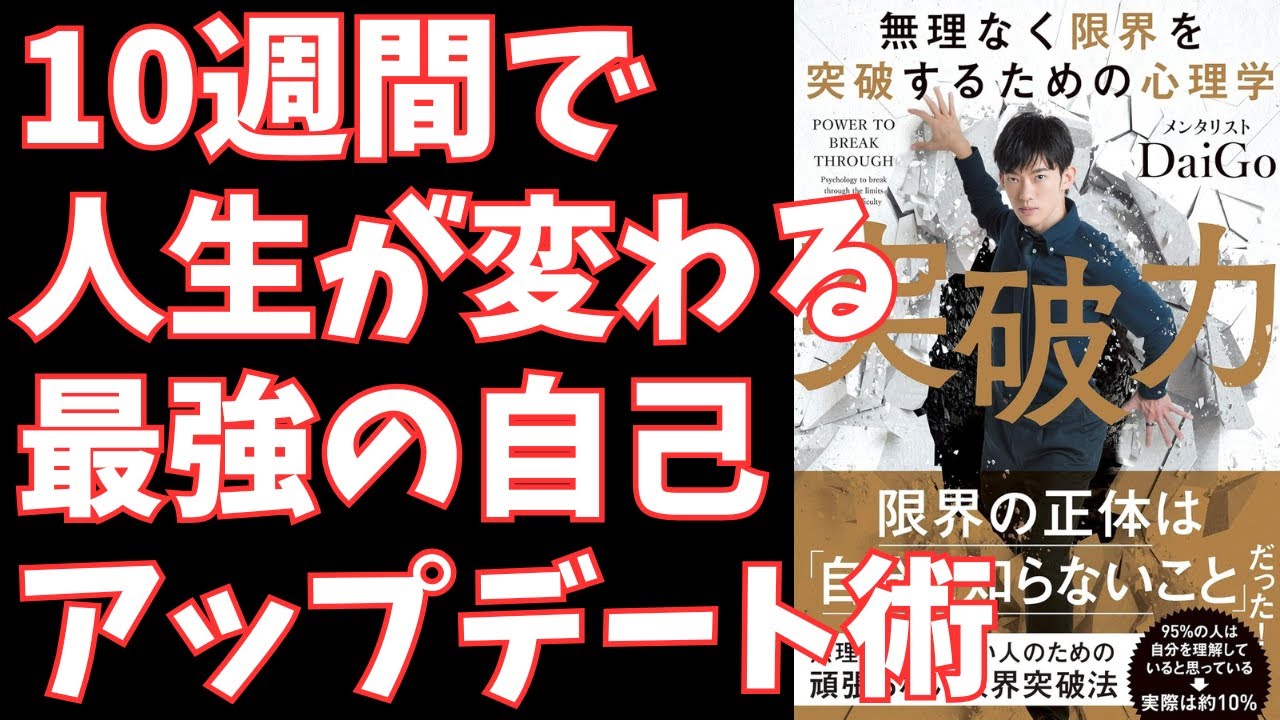養老孟司『こう考えると、うまくいく』― なぜ現代社会は“生きづらい”のか?「脳化社会」を生き抜く思考法
本書は、解剖学者である養老孟司氏の講演録を再構成した一冊です。現代社会に漂う漠然とした「生きづらさ」の正体を、人間の意識が作り出した「人工」の世界がすべてを覆い尽くした「脳化社会」という独自の視点で鮮やかに解き明かします。
この記事では、日々、予測と制御、そして「ああすれば、こうなる」という論理に追われる忙しいビジネスパーソンに向けて、その息苦しさから解放されるための「ものの見方」を、本書の具体的な事例を交えながら詳しく解説していきます。情報過多な世界で「考える」とはどういうことか、そして心に「ゆとり」を取り戻すにはどうすればよいのか、そのヒントがここにあります。
本書の要点
本書で語られる、現代社会を生き抜くための核心的なメッセージを5つのポイントにまとめました。
- 現代は「脳化社会」である:私たちの社会は、人間の意識が作り出した「人工」のルールやシステム(=都市)がすべてを覆っており、本来の「自然」が排除された、いわば脳の中の世界である。
- 「ああすれば、こうなる」という思考の限界:脳化社会では、予測と制御に基づいた「ああすれば、こうなる」という論理が絶対視される。しかし、生老病死といった人間の本質的な営みは、この論理では捉えきれない。
- 「考える」とは頭を整理すること:考える目的は、唯一の正解を見つけることではない。自分の頭の中にある情報を整理し、物事を正しく位置付けることこそが「考える」本質である。
- 私たちは二つの身体を持つ:健康診断の数値で表される一般化された「人工身体」と、一人ひとりのかけがえのない歴史を持つ「自然身体」。現代社会はこの二つの身体のバランスが崩れ、生きづらさを生んでいる。
- 「手入れ」という感覚を取り戻す:目的達成型の行動だけでなく、田んぼの世話のように、明確な目的がなくても対象を良い状態に保とうとする「手入れ」の感覚が、心にゆとりをもたらす。
なぜ、私たちの日常はこんなにも息苦しいのか?
「常に何かに追われている気がする」
「先の見えない不安で、心が休まらない」
「ロジカルに考え、効率を追求しているはずなのに、なぜかうまくいかない」
日々、仕事に邁進するビジネスパーソンの多くが、このような漠然とした生きづらさや息苦しさを感じているのではないでしょうか。その原因は、個人の能力や努力の問題だけではないのかもしれません。
本書の著者であり、解剖学者として長年人々の身体と向き合ってきた養老孟司氏は、その根本原因を「社会の成り立ちそのもの」にあると指摘します。そして、その社会を読み解くキーワードとして提示するのが「脳化社会」という概念です。
この記事では、養老氏の鋭い視点を通じて、私たちが無意識に囚われている現代社会の“常識”を問い直し、よりしなやかに、そして心にゆとりを持って生きるための思考法を探っていきます。
私たちは「脳が化けた社会」に住んでいる
本書を貫く最も重要な考え方が、「自然」と「人工」という対立軸です。
- 自然:人間が設計して作ったものではない、もともとそこにあるもの。私たちの身体や、生まれて老いて病み、死んでいくという生命現象、感情、そして天災などが含まれる。
- 人工:人間の意識(脳)が、「こうしよう」という目的や意図を持って作り出したもの。建物、道具、法律や会社の制度、そして「都市」そのものがこれにあたる。
養老氏は、現代社会を「脳化社会」と定義します。これは、人間の脳が生み出した「人工」のシステムが、本来の「自然」を覆い尽くしてしまった社会という意味です。その典型が「都市」という空間です。
都市という四角の中には自然のものは置かないというルールです。自然はいわば排除されます。たとえ木が植わっていてもそれは人が植えたものである、そこにしつらえて置いたものです。
オフィスビルや商業施設が立ち並ぶ都市空間を想像してみてください。道路は舗装され、川はコンクリートで護岸され、空調で気温は一定に保たれています。そこでは、人間がコントロールできない「自然」の要素は、徹底的に排除されています。
本書では、講演会のホールにゴキブリが現れたエピソードが紹介されます。設計者が意図していないゴキブリの出現は、この人工空間における「不祥事」であり、人々は血相を変えてそれを排除しようとします。これは、脳化社会が「自然」をいかに異物として扱っているかを象徴する出来事です。
そして養老氏は、戦後の日本は国全体がこの「都市」になったのだと喝破します。私たちは、知らず知らずのうちに、人間の脳が作り出した巨大な人工空間の中で、そのルールに従って生きているのです。
「ああすれば、こうなる」という思考のワナ
では、脳化社会(=都市)のルールとは何でしょうか。それは、「ああすれば、こうなる」という、予測と制御に基づいた行動原理です。
運動系の持っている原則は、要するに「ああすれば、こうなる」ということです。これだけです。
商売であれば、これだけ費用をかけて、これだけ売ったらいくら儲かる。
ビジネスの世界では、この思考法は不可欠です。計画を立て(予測)、KPIを追いながら実行し(制御)、目標を達成する。この繰り返しで私たちは成果を上げてきました。
しかし、この「ああすれば、こうなる」という論理が社会のすべてを支配するようになると、歪みが生じます。なぜなら、私たちの生命そのものである「自然」は、この論理では決して成り立たないからです。
まず第一に人間が生まれてきて、年を取って、病気になって死ぬ。仏教で言う生老病死ですが、これは「ああすれば、こうなる」の計算ではいきません。だいたい生まれるところが計算ではいかないわけです。
私たちは、生まれることを自分で計画したわけではありません。どんな病気になるかも、いつ死ぬかもわかりません。これらは予測も制御もできない「自然」の領域です。しかし脳化社会は、こうした予測不能なものを「問題」として扱います。「高齢化社会問題」「終末期医療問題」といった言葉が、それを象徴しています。本来当たり前であるはずの生老病死が、コントロールできないがゆえに「問題」とされてしまうのです。
この「ああすれば、こうなる」という思考は、私たちの時間感覚さえも変えてしまいました。手帳に書かれた未来の予定は、もはや変更のきかない「現在」となり、私たちの生活を縛ります。養老氏は、ミハエル・エンデの名作『モモ』を引用し、予定で未来を埋め尽くす現代社会が、子どもたちの最大の財産である「何も決まっていない未来」を奪っていると警鐘を鳴らします。
あなたは「モノ」か?「ヒト」か? – 死体から見る人間の本質
ビジネスパーソンにとって、「死体」の話は縁遠いものに思えるかもしれません。しかし、養老氏は解剖学者としての経験から、この「死体」をどう見るかという問いを通じて、人間観の本質を鋭くえぐり出します。
養老氏によれば、死体には三種類あります。
- 三人称の死体:ニュースで見るような、自分とは無関係な人の死体。これは客観的な「モノ」として認識されがちです。
- 二人称の死体:親や恋人、友人といった親しい人の死体。腹わたが出ていようと、私たちは駆け寄り、触れ、声をかけるはずです。これはもはや「モノ」ではありません。
- 一人称の死体:自分自身の死体。これは原理的に経験することができません。
現代社会、特に法律の世界では、「死んだら人はモノである。なぜなら人権がないから」と考えられがちです。しかし養老氏は、この考え方こそが人間を「人工物」として見ている証拠だと指摘します。
人工物は使われる目的によって名前を変えていいということがわかります。
(中略)
つまり死んだらモノということの裏には、生きていればヒトという条件がある。(中略)それはじつは人工のものです。脳死臨調の少数意見の表現は、人間を人工物として見た意見である。
コップが時には花瓶になり、時には凶器になるように、人工物は状況によって定義が変わります。人間も同じように「生きているときはヒト」「死んだらモノ」と定義するのは、人間を社会的な役割や機能で判断する「人工物」として捉えているからです。
しかし、私たちは本来、誰かに設計されたわけではない「自然」の存在です。この根本的な事実を忘れると、私たちは自分や他人を、機能や生産性といった一面的な尺度でしか見られなくなってしまうのかもしれません。
二つの身体 -「人工身体」と「自然身体」のあいだで
私たちは、知らず知らずのうちに二つの身体を持っている、と養老氏は言います。
一つは「人工身体」です。これは、健康診断の結果表に並ぶ数値のように、一般化・普遍化・数値化された身体のことです。血圧や血糖値は「正常値」という基準で判断され、そこから外れると「異常」とされます。現代の医療制度は、この「誰の身体も同じ基準で測れる」という人工身体を前提に成り立っています。臓器移植が可能だと考えられるのも、個々の身体を交換可能なパーツとして捉える「人工身体」の視点に基づいているのです。
身体については人並み、頭については人並みはずれろという。これは無理な話でして、なぜかと言えば頭も身体の内だからです。
養老氏が指摘する現代社会の矛盾はここにあります。身体については「正常値(人並み)であれ」と求められる一方で、入学試験に象徴される脳の機能については「人並み外れて優秀であれ」と要求される。このねじれが、多くのビジネスパーソンが抱えるストレスの根源にあるのではないでしょうか。
もう一つは「自然身体」です。これは、「かけがえのない」、一回限りの歴史性を持った身体です。どこで生まれ、何を食べて育ち、どんな経験をしてきたか。同じ人間は二人といないように、私たちの身体も唯一無二の存在です。この自然身体と向き合うのが、末期医療などで重視される「ケア」の領域です。そこには一般的な正解はなく、その人自身の人生に寄り添うことしかできません。
現代社会は「人工身体」の視点に偏りがちですが、私たちはこの二つの身体のバランスの中で生きています。このことを自覚するだけでも、画一的な健康法や成功法則に振り回されず、自分自身の心と身体の声に耳を傾けるきっかけになるはずです。
「考える」とは答えを探すことではない
情報が溢れ、常に「正解」や「最適解」を求められる現代。私たちは「考える」という行為そのものについて、誤解しているのかもしれません。養老氏は、考えることの本質を次のように語ります。
考えるのは、答えを得るためではない。頭の中で問題をきちんと位置付けるためである。答えは関係ない。答えは出ることも、出ないこともある。(中略)問題が正しく位置付けられていれば、おのずから答えが出る。そのために自分の頭を整理しているのである。
私たちはつい、他人の意見を聞いたり、本を読んだりすれば「答え」が見つかると思いがちです。しかし、重要なのは他人の頭ではなく、自分の頭の中を自分で整理すること。養老氏は「みんなで考えましょう」という日本的な風潮にさえ、「考えるのは自分に決まっている」と疑問を呈します。
また、長嶋茂雄氏の例を挙げ、物事の理解には二つの側面があることを示します。長嶋氏は物理学の理論を説明できなくても、誰よりも物理法則に則った実践(ホームラン)ができました。これは、身体に染み付いた無意識のプログラム(ソフト)を縦に深めていった結果です。一方、物理学者が理論を説明できるのは、そのソフトを横から見て分析しているからです。しかし、分析しすぎると、かえって実践(運動)ができなくなることもあります。
意識的な理解(理屈)と、無意識的な実践(感覚)。
この両方が存在することを認め、性急に白黒つけようとしないことが、複雑な問題と向き合う上で重要なのかもしれません。
ゆとりを取り戻すヒント – 「手入れ」という感覚
では、「ああすれば、こうなる」という予測と制御の世界に疲れた私たちは、どうすれば心に「ゆとり」を取り戻せるのでしょうか。本書が提示するヒントは、「手入れ」という言葉に集約されています。
「手入れ」という言葉なんですが、今、手入れというと、ほとんどの人が警察の手入れだと思っているんですね。(中略)この手入れって、非常におもしろい言葉なんです。
(中略)
田んぼがそうだと思います。お百姓さんは、いい稲をつくるのはもちろん大きな目的ですが、(中略)何か当面そうしないと気が済まないからやっているんですけども、そういうふうにしていくと、何と最終的には、外国人がびっくりするような、きれいな景色ができてまいります。
手入れとは、明確な目的達成のためというより、対象を良い状態に保つために、継続的に手を加える行為です。そこには「ああすれば、こうなる」という жесткий な計算はありません。植木屋が枝を剪定するのも、女性が日々お化粧をするのも、この「手入れ」の感覚に近いと養老氏は言います。
そして、この感覚は「子育て」にも通じます。
私は子どもを育てるって、そういうことじゃないかなと思います。自然に手入れをしている。我々の体も自然ですから、自分のつくったものじゃないですから。(中略)手入れというのは、もともとあったものを認めておいて、それに何か人間の手を加えていくということです。子どもが典型的にそうだと思います。
子どもを自分の思い通りに「制御」しようとするのではなく、その子自身の「自然」な姿を認め、より良く育つように寄り添い、手を加えていく。これが「手入れ」としての関わり方です。
ビジネスの世界でも、部下の育成やチームマネジメントにおいて、この「手入れ」の感覚は応用できるのではないでしょうか。短期的な成果(ああすれば、こうなる)だけを求めるのではなく、相手の成長を長い目で見守り、環境を整え、必要なサポートをする。そんな関わり方が、結果的に強い組織を作っていくのかもしれません。
まとめ:脳化社会の歩き方
養老孟司氏の『こう考えると、うまくいく。』は、単なる生き方のノウハウ本ではありません。それは、私たちが当たり前だと思っている世界の「見方」そのものを問い直す、哲学の書です。
「自然」と「人工(意識)」というシンプルな物差しを持つことで、複雑に見えた現代社会の問題が、驚くほどクリアに見えてきます。
もしあなたが日々の仕事や生活に息苦しさを感じているなら、それはあなたが「脳化社会」のルールに忠実すぎるからかもしれません。一度立ち止まり、予測と制御の世界から少しだけ距離を置いてみませんか。自分の身体の声に耳を傾け、理由もなく惹かれるものに時間を使い、誰かを「手入れ」するように関わってみる。
その小さな一歩が、この予測不能な時代をしなやかに生き抜くための、大きな力となるはずです。