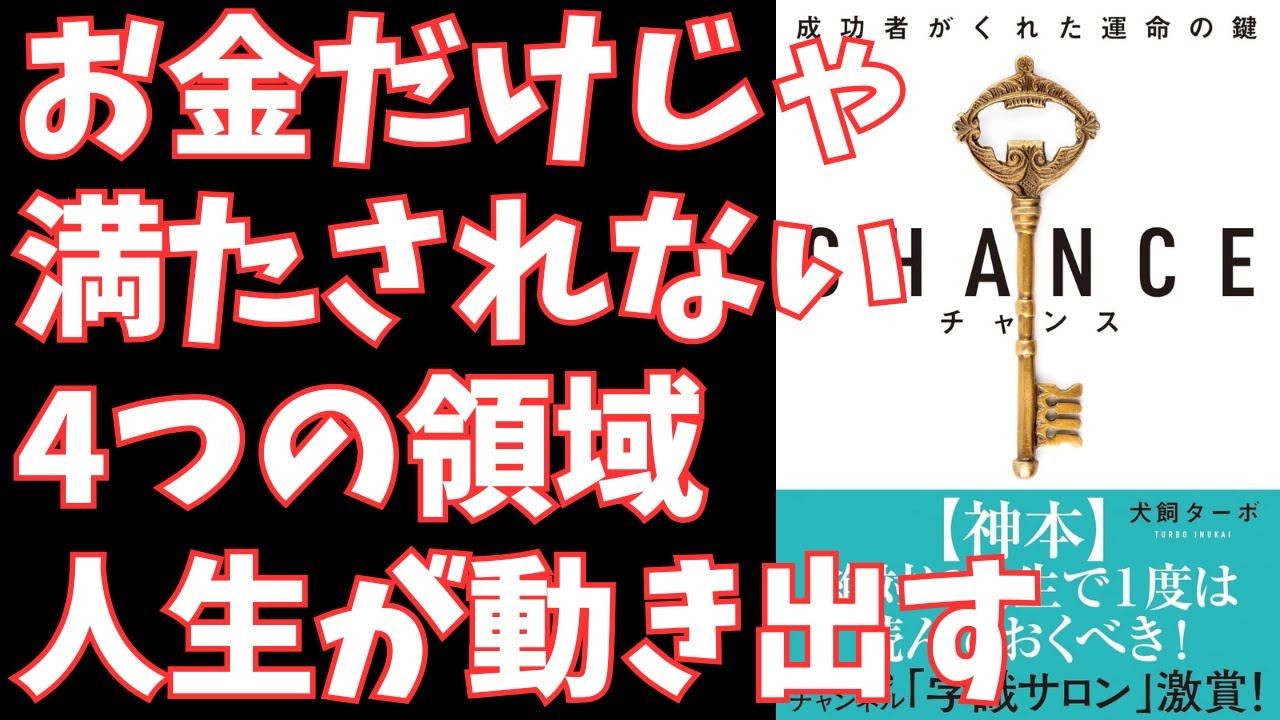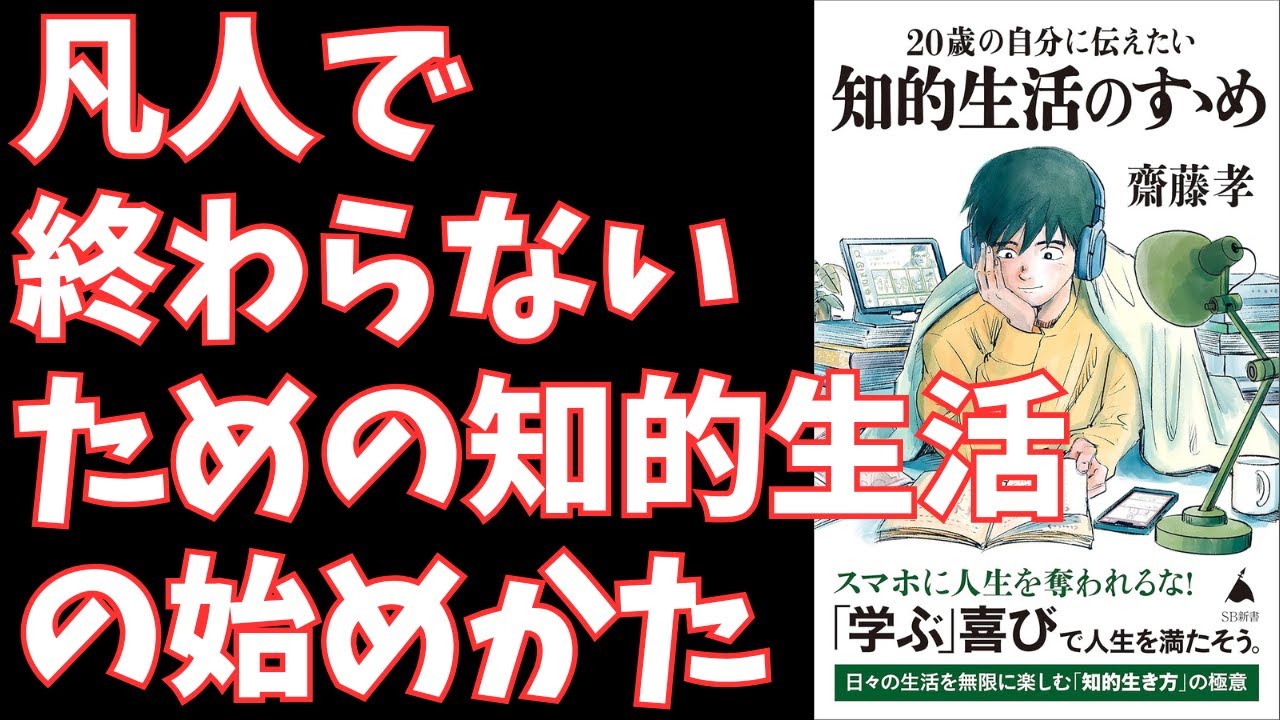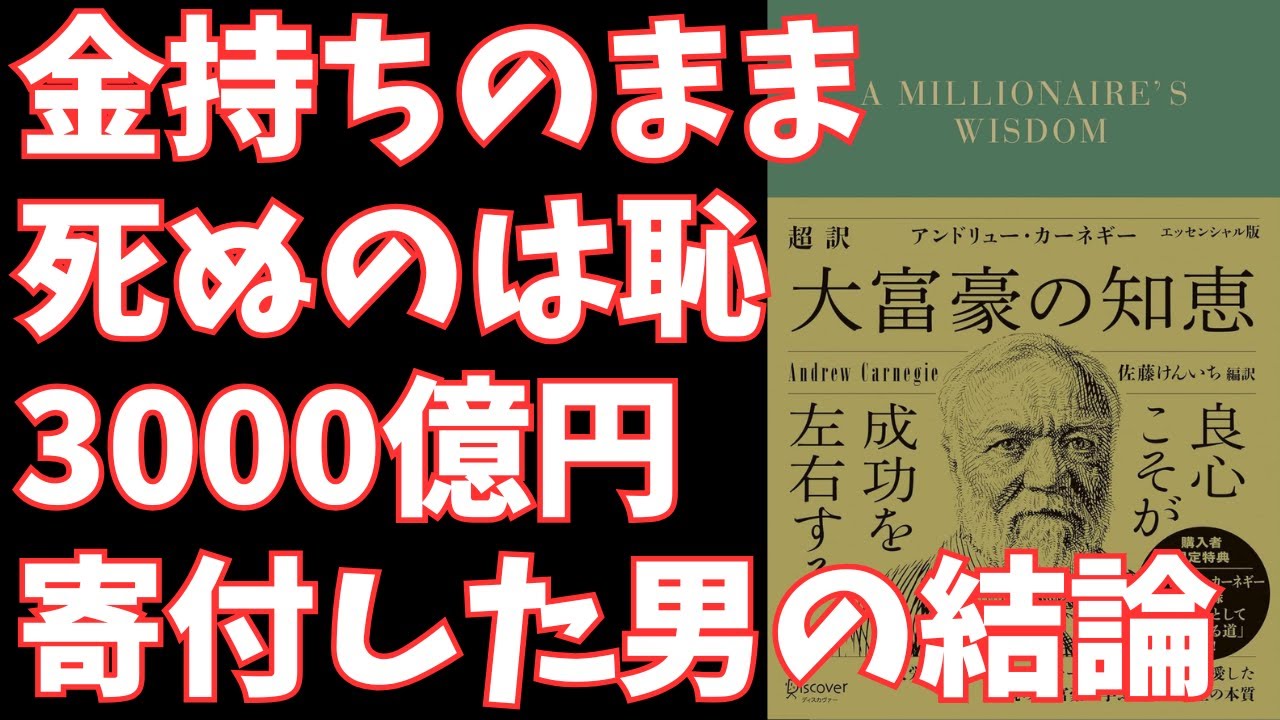『「お金が貯まる家」にはものが少ない』に学ぶ、忙しいビジネスパーソンのための時間とお金を生み出す片づけ術
本書『「お金が貯まる家」にはものが少ない』は、片づけのプロでありファイナンシャルプランナーでもある下村志保美氏が、「家計と片づけの相関関係」を解き明かし、ものが少ない家がなぜお金が貯まるのかを具体的に解説した一冊です。
この記事では、本書のエッセンスを抽出し、特に時間に追われるビジネスパーソンが日々の生活や仕事に活かせる「時間」と「お金」を生み出すための思考法と実践術を、具体的な事例と共に詳しくご紹介します。部屋を片づけることが、いかに思考を整理し、生産性を高め、経済的な余裕をもたらすか、そのメカニズムを学んでいきましょう。
本書の要点
- ものを減らすことは、あなたの時間・場所・手間を盗む「3人の泥棒」を追い出し、浪費を防ぐ最高のトレーニングである。
- 「安いから」「お得だから」という他人軸の選択をやめ、自分にとって本当に「使いたい」ものだけを選ぶことで、ムダな出費が自然となくなる。
- ものを所有するには「場所代」という最も高価なコストがかかる。この意識を持つだけで、ものの見極めが加速し、不要なものを手放せるようになる。
- 片づけや家計管理は完璧を目指さない。「ここに入るだけ」という物理的な「枠」と予算の「枠」を設定し、仕組み化することで、無理なく継続でき、自然とお金が貯まる体質に変わる。
- 片づけとは、自分にとって大切なものを見つける行為。不要なものを手放す痛みを知ることで、安易にものを増やす浪費行動にブレーキがかかる。
なぜ、デキるビジネスパーソンの家には「ものが少ない」のか?
「仕事がデキる人のデスクはきれいだ」とよく言われます。情報が整理され、必要なものにすぐにアクセスできる環境は、思考をクリアにし、生産性を高めるからです。実はこの原則、デスクの上だけでなく「家」という空間全体にも当てはまります。
多忙な日々を送るビジネスパーソンにとって、時間は最も貴重な資源です。しかし、家がものであふれていると、この貴重な資源が知らず知らずのうちに奪われていきます。
本書の著者、下村志保美氏は、この無意識の浪費の正体を「3人の泥棒」と表現しています。
時間泥棒:探し物をするムダな時間
「あの書類はどこだっけ?」「着ていく服が見つからない…」ものが多い家では、探し物にかかる時間が積み重なり、人生の貴重な時間を浪費します。1日に5分探し物をしたとすれば、1年で約30時間。これは丸1日以上の時間を失っている計算になります。ビジネスの世界でタイムパフォーマンスが重視されるように、プライベートの時間も効率化することが、結果的にキャリアや自己投資の時間を生み出すのです。場所泥棒:不要なものを置くスペースのコスト
本書で最も衝撃的な指摘の一つが、この「場所泥棒」の存在です。私たちは家賃や住宅ローンという形で「場所代」を支払っています。もし、その貴重なスペースが「使っていないもの」で占領されているとしたら、それは不要品のために高額な家賃を払い続けているのと同じことです。本書では、具体的な計算が示されています。例えばあなたが70平米・4000万円で購入した3LDKのマンションに住んでいるとします。そのうち6畳分の一部屋を「使っていないもの、整理しきれていないもの」の置き場所に使っているとしたら……? (中略)つまり555万円分を、要らないものに費やしていることになります。
この事実をどう受け止めるでしょうか。555万円分の資産が、ただのガラクタ置き場になっている。このコスト意識を持つだけで、ものを安易に家に入れることへの抵抗感が生まれるはずです。手間泥棒:多すぎるものの管理に費やす労力
ものが多ければ多いほど、その管理には手間がかかります。「衣替えのたびに大量の服をクリーニングに出す」「たくさんの食器を洗う」「掃除のたびに床のものをどかす」…これら一つひとつは小さな手間でも、習慣化されると気づきにくい「手間泥棒」となります。
著者は、家事にも時給の概念を持つことを提案しています。不要なものを管理する手間を減らせば、家事の総時間が減り、自分の時間あたりの価値(時給)が上がります。その時間を休息や自己投資に回せば、生活全体の質が向上するのは言うまでもありません。
このように、ものが少ない家は、単にスッキリしているだけでなく、時間、お金、労力というビジネスパーソンにとって重要なリソースの浪費を根本から防ぐ、極めて合理的な環境なのです。
お金持ちの思考法を真似る!「引き算」で空間価値を最大化する
映画やドラマで描かれる「お金持ちの家」を思い浮かべてみてください。高級な家具はあっても、生活感のあるものがごちゃごちゃと置かれているシーンは少ないはずです。本書によれば、これは演出上の都合だけでなく、現実を反映しています。
資産を多く保有している人ほど、家の中はスッキリと片づいています。これは、お金持ちはものを買う時に「これが本当に必要なのかどうか」をしっかりと吟味するクセがついているから。
成功している人ほど、空間の価値を熟知しています。限られたスペースにものを一つ置くことは、他の可能性を一つ失うことと同義です。だからこそ、彼らはものを増やす「足し算」ではなく、不要なものを削ぎ落とす「引き算」の思考を徹底しています。
私たちもこの思考法を取り入れることができます。何かを買おうと思ったとき、「これを置くスペースのコストはいくらか?」「これを管理する手間は?」と自問自答するクセをつけるのです。
特に陥りがちなのが、「お客様用の布団」のような「いつか使うかもしれない」もののワナです。一年に数回しか使わないもののために、クローゼットの大部分を占領させておくのは、まさに「場所泥棒」にスペースを提供している状態。現代では、布団のレンタルサービスなど、必要な時に必要なだけ利用できる便利なサービスが充実しています。お金持ちはこうしたサービスを上手く活用し、「所有」することのリスクとコストを回避しているのです。
この「引き算」の思考は、買い物の仕方にも大きな影響を与えます。例えば、ネットスーパーの活用もその一つ。
「送料がもったいない」「実物を見たい」と感じるかもしれません。しかし、スーパーを何軒もはしごする時間、重い荷物を運ぶ労力、そして店内で「ついで買い」してしまう衝動的な浪費…。これらを総合的に考えると、ネットスーパーは最高のタイムパフォーマンスとコストパフォーマンスを両立させる買い物テクニックと言えます。
「でも」「だって」という言い訳を封印し、まずは新しい習慣を試してみる。この小さな一歩が、浪費体質から貯蓄体質へと変わるための重要な転換点となるのです。
「見栄」を捨て「自分軸」を取り戻すクローゼット改革
ビジネスパーソンにとって、服装は自己表現であり、信頼を勝ち取るための重要なツールです。しかし、そのクローゼットが「着ない服」であふれかえってはいないでしょうか。
「私はこんなに洋服を持っているのに、いつも着ていく服がないんです」
これは、片づけに悩む多くの人が口にする言葉です。その原因は、自分軸がブレていることにあります。「流行っているから」「あの人が着ていて素敵だったから」という他人軸で服を選び続けると、クローゼットはテイストのバラバラな服であふれ、結果的に「着る服がない」状態に陥ります。
本書が提唱するのは、「似合わない10着より、似合う1着を」という哲学です。そのために有効なのが、以下のステップです。
ステップ1:服の「賞味期限」を知る
かつて高価だったブランド品や、思い出の詰まった一着。手放しがたい気持ちはわかります。しかし、服にはデザインの流行り廃りだけでなく、素材の劣化という物理的な「賞味期限」が存在します。
何年も着ていない服は、一度袖を通し、鏡の前ではなくスマホで写真を撮ってみることを著者は推奨しています。客観的に見ることで、「今の自分には似合わない」という現実を直視できるからです。
それでも迷うなら、「この服を着て、新しい服を買いに行けるか?」と自問してみてください。自信を持って「YES」と言えないなら、その服の役目は終わっているのです。
ステップ2:買い物の失敗を「仕組み」で防ぐ
特にネット通販での洋服のポチ買いは失敗の元。著者は自身の経験から、「通販で洋服を選ぶのは難しい」と断言しています。それでも利用する場合は、「返品の手間」をあえて利用するという逆転の発想を提案します。
サイズで迷ったら、MとLの両方を取り寄せる。そして、似合わない方を必ず返品するのです。この「返品する」というひと手間が、安易な買い物の強力なストッパーになります。「そこまでして買うべき服か?」と冷静に判断するクセがつき、本当に必要なものだけが手元に残るようになります。
ステップ3:「ハンガー」に投資し、クローゼットの総量を決める
クローゼットがごちゃつく原因の一つに、クリーニング店でもらったバラバラのハンガーがあります。高さも色も形も違うハンガーは、視覚的なノイズとなり、「片づいていない」印象を増幅させます。
そこで著者が推奨するのが、「お金をかけてハンガーをそろえること」です。
例えば、ニトリのハンガーで100本そろえても約1万円。これを「高い」と感じるか、「投資」と捉えるかが分かれ道です。
ハンガーを統一することで、「洋服は、このハンガーの数だけ」という物理的な「枠」が生まれます。この枠を超えそうになったら、何かを手放さなければならない。このシンプルなルールが、無駄な服が増えるのを自動的に防いでくれるのです。
これは、プロジェクトの予算やリソースを管理するビジネスの考え方と全く同じです。枠を決めることで、最適なリソース配分が可能になります。
クローゼットは、あなたの価値観が最も表れる場所。見栄や執着を手放し、本当に自分を輝かせてくれる服だけを選ぶ。そのプロセスは、仕事における意思決定のトレーニングにもなるはずです。
生産性を下げる「見えない敵」を一掃するリビング・キッチン術
リビングやキッチンは、家族が集まる場所であると同時に、ものが散らかりやすい場所でもあります。散らかった空間は、集中力を削ぎ、無意識のうちにストレスを溜め込む原因となります。ビジネスで最高のパフォーマンスを発揮するためには、心身を休める家の環境が不可欠です。
リビング:「ルンバが走り回れる床」が基準
本書では、片づいていない家に限って、ルンバのような高級家電がホコリをかぶっていることが多いと指摘されています。ものが床にあふれていては、せっかくのロボット掃除機も活躍できません。
目指すべきは「ロボット式掃除機がストレスなく走り回れる空間」。これは、床にものが置かれていない状態の比喩です。
床にものが増えていくプロセスは、こうです。
1. 置きやすいダイニングテーブルに「とりあえず」置く。
2. テーブルがいっぱいになり、キッチンカウンターへ移動。
3. カウンターもいっぱいになり、棚の上へ。
4. 最終的に、平面である「床」が最後の置き場所に。
この連鎖を断ち切るには、「とりあえず置き」をやめるしかありません。そのために効果的なのが、書類整理の仕組み化です。
多くの家庭で魔窟と化している「一時置きボックス」。これは便利に見えて、ただ問題を先送りにしているだけです。
解決策は、郵便物が届いたら「その場で開封し、不要なものは即捨てる」こと。そして、提出が必要な書類は、クリアファイルに入れて「提出待ちボックス」に立てて収納します。中身が見えることで、処理忘れを防ぎ、探す手間もなくなります。
この情報処理能力は、ビジネスにおけるタスク管理や情報整理のスキルと直結します。
キッチン:「あったら便利」は「なくても平気」
キッチンには、「便利そう」な調理器具や、使いかけの調味料があふれがちです。しかし、本当にそれらすべてが必要でしょうか?
著者は「ドレッシングは1種類でいい」「中濃ソースやケチャップは常備していない」と語ります。自分や家族の食生活を見直し、「ないと困るもの」と「あれば使うかもしれないもの」を区別することが重要です。
特に陥りがちなのが、「ていねいな暮らし」プレッシャーです。SNSなどで見る理想の生活に憧れ、手作り味噌の樽や、使いこなせない便利家電を買ってしまう。しかし、それがプレッシャーとなり、使いこなせない自分に罪悪感を抱いていては本末転倒です。
理想を追うのではなく、今の自分のライフスタイルに合った、最も管理が楽な状態を目指すこと。それが、結果的に時間と心の余裕を生み出します。
例えば、著者は炊飯器とオーブントースターを持たず、鍋とフライパンで代用しているそうです。これは極端な例かもしれませんが、「これは本当に必要か?」と既存の常識を疑う視点が、ものを減らす上で非常に重要であることを示唆しています。
リビングやキッチンを整えることは、日々の生産性を高めるための環境整備です。ノイズの少ない空間は、クリアな思考と集中力を生み出し、仕事のパフォーマンス向上にもつながるでしょう。
お金の流れを整える!財布と家計のミニマリズム
部屋の片づけが物理的な環境整備だとすれば、家計の管理は「お金」の流れを整えることです。本書では、この二つは密接に連動していると繰り返し述べられています。ものが貯まらない家は、お金も貯まらないのです。
「お金持ちの財布」を真似る
まず、あなたの財布の中を覗いてみてください。パンパンに膨らんだレシート、使っていないポイントカード、複数のクレジットカードで満杯になっていませんか?
本書が提案するのは「お金持ちの財布を真似る」こと。それは、ブランド物の財布を持つことではなく、中身がスッキリしている状態を真似ることです。
- レシートはその日のうちに処分する: レシートを溜めて家計簿をつける行為は、それ自体がお金を生むわけではありません。むしろ、「家計管理をしている」という満足感だけで終わってしまいがちです。キャッシュレス決済の履歴を活用すれば、支出の管理はもっとスマートにできます。
- ポイントカードは厳選する: ポイントカードは、出費の象徴です。「ポイント〇倍デー」に踊らされて不要なものまで買ってしまうのは、節約ではなく浪費です。本当によく使う店のカードだけに絞り、アプリ化できるものはすべてスマホに移行しましょう。著者はこの習慣を見直しただけで、月2万円の節約に成功したそうです。
- クレジットカードは1枚に絞る: 複数のカードは、引き落とし日がバラバラになり、家計管理を複雑にします。また、不正利用のリスクも高まります。自分のライフスタイルに最も合ったカードを1枚選び、そこに支出とポイントを集約するのが最も合理的です。
最強の貯金術は「先取り貯金」
節約や家計管理において、最も重要な原則は「月の予算を決めること」と「先取り貯金」です。
給料が入ったら、まず貯金する額を別の口座に移してしまう。そして、残った金額の範囲内で生活する。このシンプルなルールを守るだけで、お金は確実に貯まっていきます。
これは収入の多い少ないに関係ありません。高収入でも予算管理ができていなければお金は残りませんが、収入がそれほど多くなくても、この仕組みさえ作ってしまえば、着実に資産を形成できるのです。
これは、プロジェクト管理における「最初にバッファを確保し、残りのリソースでタスクを完了させる」という考え方に似ています。最初に目的(貯金)を確保することで、日々の細かな節約に一喜一憂することなく、精神的な安定を得ながら目標を達成できるのです。
部屋も、財布も、家計も、基本は同じです。「枠」を決めて、不要なものをそぎ落とし、流れをシンプルにする。この原則を徹底することが、経済的な自由への第一歩となります。
まとめ:「まだ使える」から「まだ使いたい」へ – 思考をシフトし、豊かな人生を手に入れる
ここまで、本書『「お金が貯まる家」にはものが少ない』を基に、片づけがいかに私たちの時間、お金、そして思考に影響を与えるかを見てきました。
本書の根底に流れる最も重要なメッセージは、片づけとは単なる整理整頓ではなく、「自分にとって本当に大切なものを見極める最高のトレーニング」であるということです。
ものを手放すとき、私たちは「まだ使えるのにもったいない」という罪悪感に苛まれます。しかし、著者はこう問いかけます。
私がものを整理する時に大切にしているのは「私は今、これを大事に使いたいと思っているか?」ということ。その時に「まだ使えるし……」という気持ちが出てきたら、そのものとの関係はおしまいの時。
「まだ使える」は、「もう使いたくない」の裏返しなのです。
本当に心から「使いたい」と思えるものだけに囲まれた生活は、日々の満足度を大きく高めてくれます。それは、仕事においても同様です。「やらなければならない(Can)」タスクに追われるだけでなく、「本当にやりたい(Will)」ことに時間とエネルギーを注ぐ人生につながっていくでしょう。
そして、ものを減らすことは、未来の自分や、残された家族への「思いやり」でもあります。万が一、自分に何かあったとき、大量のものに埋もれた部屋の片づけを誰かに託すことになります。防災の観点からも、ものが少ない家は、いざという時の避難をスムーズにし、復興を早めます。
この本を読み終えた今、ぜひあなたの目の前にあるものを一つ、手に取ってみてください。そして、「これは本当に必要か?」「これを置いているスペースに、いくら払っているか?」「これは、まだ使いたいものか?」と問いかけてみてください。
その小さな一歩が、あなたの家を、そして人生を、より豊かで生産的なものに変えていく始まりとなるはずです。